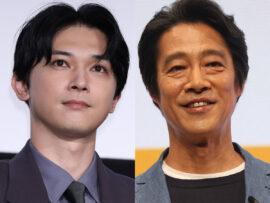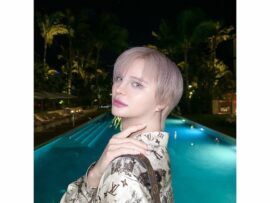近年、すき家、焼肉きんぐ、くら寿司など、人気外食チェーン店でのトラブルが相次いで報道されています。異物混入、衛生問題、顧客対応の不手際…これらの問題は、私たち消費者に不安を与え、外食産業全体への不信感にもつながりかねません。一体何がこれらの問題を引き起こしているのでしょうか?そして、私たちはどう向き合っていけば良いのでしょうか?この記事では、その背景や影響、そして私たちが取るべき行動について考えていきます。
問題の背景にある「生産性向上」と人手不足
 alt
alt
外食チェーン店では、効率化と利益追求のため「生産性向上」が常に求められています。しかし、その結果として人手不足が深刻化し、従業員一人当たりの負担が増大している現状があります。十分な人員が確保できないまま、多くの顧客に対応しなければならないため、トラブル発生時の対応が遅れたり、適切な衛生管理が行き届かなかったりするケースも少なくありません。
安すぎる価格設定がもたらす負の連鎖
古舘伊知郎氏も指摘するように、外食チェーン店の価格設定は、原価高騰の現状を考えると「安すぎる」と言えるかもしれません。低価格競争の中で、企業は人件費や食材費を削減せざるを得ず、それがサービスの質の低下やトラブル発生の一因となっている可能性も考えられます。飲食業界専門家の山田太郎氏(仮名)は、「価格を適正に見直すことで、従業員の待遇改善や食材の品質向上につながり、結果的に顧客満足度の向上にも寄与するだろう」と述べています。
適正価格の実現に必要なのは「手取りの増加」
では、どのように価格を適正化していくべきでしょうか?古舘氏は、「一にも二にも手取りを増やさなければいけない」と主張し、景気対策の必要性を訴えています。消費者の購買力が高まれば、外食産業も値上げを行いやすくなり、サービスの質の向上にもつながる可能性があります。
私たち消費者ができること
これらの問題に対して、私たち消費者はどのような行動を取ることができるでしょうか?まずは、問題意識を持つことが大切です。安さだけを追求するのではなく、サービスの質や従業員の労働環境にも目を向け、企業の姿勢を評価していく必要があります。また、SNSなどで情報を共有し、問題提起をすることも重要です。消費者の声が企業の行動を変える力となる可能性もあります。
まとめ:持続可能な外食産業のために
外食チェーン店でのトラブルは、企業側の問題だけでなく、私たち消費者にも責任があると言えるかもしれません。価格、サービス、労働環境など、様々な側面から問題を捉え、持続可能な外食産業の実現に向けて、企業と消費者が共に考えていく必要があるのではないでしょうか。