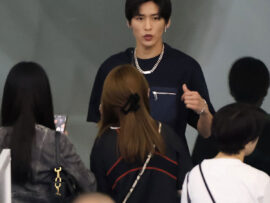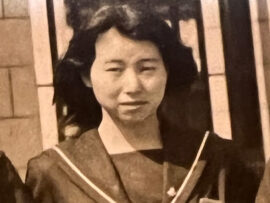大学受験は多くの10代にとって人生における大きな節目となります。現在の日本社会では、進学する大学が良いとされるほど、希望する職業に就ける可能性が高まり、将来の選択肢が増える傾向にあります。それほど大学受験の持つ影響力は大きいと言えます。しかし、少子化が進む中で「大卒」という肩書きの価値はどのように変化しているのでしょうか。そして、これからの学生は大学進学についてどのように考えれば良いのでしょうか。このテーマについて、著書『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』を出版したびーやま氏へのインタビューから得られた知見を基に考察します。
少子化がもたらす「大卒」の価値低下
びーやま氏は、現代において「大卒」という広いくくりでの価値は、かつてに比べ確実に下がっていると指摘しています。70代以上の世代が学生だった頃は、大学に進学すること自体がエリートとされる時代でしたが、現在はそうではありません。全国的に学生の定員割れを起こしている、いわゆる「ボーダーフリー(BF)」の大学が増加傾向にあることも、大卒という肩書きの価値が相対的に低下した一因です。選ばなければ誰でも大卒になれる時代になった、というのが現状認識です。
評価基準の変化:「どこ大卒か」「何を学んだか」がより重要に
一方で、今後大卒に価値がなくなるわけではないとびーやま氏は考えます。ただし、「どんな大学を卒業したのか」「大学で何を学んできたのか」が、これまで以上に厳しく見られるようになるとしています。ただ大卒であることの価値が下がった結果、難関大学や名門大学でなければ意味がないという風潮が強まっています。社会も「大卒かどうか」ではなく、「どこの大学を卒業したか」で判断することが一般的になってきており、「学歴フィルター」はその典型的な例です。
多様な入試制度と個人の能力への焦点
しかし、名門大学においても指定校推薦など多様な入試制度が導入されたことで、学生のレベルにばらつきが見られるようになっています。このため、今後は「名門大だから素晴らしい」という見方も薄れ、個人の能力がより重視されるようになるとびーやま氏は予測します。
 大学受験に向けて勉強する学生の手元のイメージ
大学受験に向けて勉強する学生の手元のイメージ
今後の学生が進むべき道:本質は「学び続けること」
それでは、これからの時代を生きる学生は、大学進学についてどのように考えるべきなのでしょうか。びーやま氏は、個人的な意見として、その本質は「普通に勉強して良い大学に入り、入学後もきちんと勉強を続けること」にあると述べています。大卒の価値が全体として下がったとしても、それは努力する学生を評価しないという意味ではありません。むしろ、全体のレベルが下がったからこそ、真面目に学業に取り組む学生の価値は以前より高まっていると見ています。このような学生は、いつの時代も社会から求められる人材であると考えられます。
また、学歴だけでなく、特定の資格を取得している、あるいは何らかの実績を持っている学生も、これからの社会では適切に評価されるでしょう。現代社会は、学歴以上に実力が重視される方向にシフトしており、この傾向は今後さらに強まる可能性が高いです。
結論:変化への適応と主体的な学びの重要性
現代日本において、「大卒」という肩書きが持つ絶対的な価値は確かに変化しています。しかし、これは大学で得られる学びや経験そのものの価値が失われたことを意味しません。社会は、どの大学を卒業したか、そしてそこで何をどのように学んだか、さらに卒業後に何を身につけたのかをより厳しく評価するようになっています。
これからの時代、大学進学を考える学生には、単に「大卒」という肩書きを得るためだけでなく、大学という環境で何を学び、どのような能力を身につけたいのかを主体的に考え、入学後も学び続ける姿勢が求められます。学歴だけでなく、個人の実力や培ってきた経験が評価される「実力社会」への変化に適応し、自身の価値を高めていくことが、将来の選択肢を広げる鍵となるでしょう。