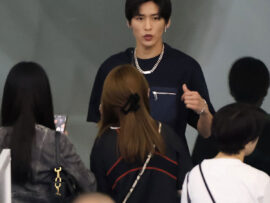日台が極超音速ミサイルの開発・配備を加速させており、東アジアの安全保障環境が大きく変化しようとしています。マッハ5以上のスピードと変則的な軌道で既存の迎撃システムを突破するこの兵器は、中国・ロシアが先行していましたが、中国の軍事的圧力増大を受け、日台も対抗措置に乗り出しています。この動きは、東アジアにおける新たな軍拡競争の火種となるのでしょうか?
日本の極超音速ミサイル開発:島嶼防衛から戦略的抑止力へ
日本は2024年初頭から、島嶼防衛用高速滑空弾「ブロック1」を実戦配備する予定です。射程距離900kmとされるこのミサイルは、沖縄配備で台湾海峡をカバーし、中国の侵攻を抑止する狙いがあります。さらに、射程2000kmの「ブロック2A」(2027年開発完了予定)、射程3000kmの「ブロック2B」(2030年まで登場予定)も開発中で、中国本土への攻撃力強化を図っています。
 alt極超音速ミサイルの概念図。その速度と軌道は、従来の防衛システムにとって大きな脅威となる。(出典:朝鮮日報日本語版)
alt極超音速ミサイルの概念図。その速度と軌道は、従来の防衛システムにとって大きな脅威となる。(出典:朝鮮日報日本語版)
三菱重工業は量産体制を強化し、開発完了前からの生産開始という異例のスピードで配備を進めています。これは、中国の台湾侵攻リスクの高まりを強く意識したものと言えるでしょう。軍事評論家の田中一郎氏(仮名)は、「日本は中国の軍事力増強に対抗し、抑止力を高める必要に迫られている」と指摘します。
台湾の極超音速ミサイル「青天2」:北京を射程に収める戦略兵器
台湾も極超音速ミサイル開発に力を入れています。中山科学研究所が開発中の「青天2」は、最大射程2000kmとされ、中国の首都北京をも射程圏内に収めます。これは、有事の際に中国本土への反撃能力を示すことで、抑止効果を高める狙いがあると見られます。
極超音速ミサイル:東アジアの新たな軍拡競争の火種となるか?
日台の極超音速ミサイル開発は、中国の軍事戦略に大きな影響を与える可能性があります。中国国内では、ウクライナ紛争における西側供与の長距離ミサイルによるロシア本土攻撃を参考に、日台も同様の戦略を取る可能性が懸念されています。
中国は、日米が開発中の極超音速ミサイル迎撃システム「GPI」や、日本の新型宇宙ステーション補給機「HTV-X」による極超音速ミサイル探知実験を警戒しており、対抗策として新型レーダー開発を進めているとされています。
海軍大佐出身の中国軍事評論家、曹衛東氏は、日本の極超音速ミサイル開発成功は、同国が技術を確立したことを意味し、周辺国も追随する可能性を指摘しています。また、徹甲弾搭載の極超音速ミサイルは中国の空母や大型上陸艦への脅威となるとも分析しています。
東アジアの軍事バランスは新たな局面へ
日台による極超音速ミサイル開発は、東アジアの軍事バランスに大きな変化をもたらす可能性があります。各国が新たな兵器開発や防衛システム強化に動き出すことで、軍拡競争が激化する懸念も拭えません。今後の動向に注視していく必要があります。