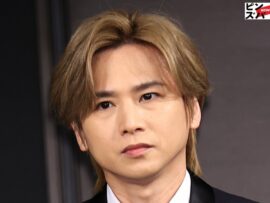提供精子・卵子を用いた不妊治療をめぐり、当事者から不安と批判の声が上がっています。今国会に提出された「特定生殖補助医療法案」は、子の出自を知る権利を保障する目的で制定されたはずですが、本当に当事者の思いは汲み取られているのでしょうか?本記事では、90歳の精子提供者の後悔や、AIDで生まれた子の苦悩を通して、法案の問題点を探ります。
90歳男性の告白:出自を知らされないAIDは子どもに不幸を招く
「AIDに協力したことを後悔している」。そう語るのは、64年前に精子を提供した中田満義さん(仮名、90歳)です。産婦人科医の息子として育ち、不妊に悩む夫婦の切実な思いに触れてきた中田さんは、青年時代にAIDに積極的に協力しました。しかし、今になって、出自を明らかにしないAIDは子どもに不幸を招き、提供者自身も無責任だったと痛感しているといいます。
 精子提供のイメージ
精子提供のイメージ
中田さんは、AIDで生まれた人が自身を探し出して連絡を取ってきた際には、誠実に対応するつもりです。しかし、生まれた子には中田さんを知る術がありません。この現状に、中田さんは深い後悔の念を抱いています。
問題点だらけの特定生殖補助医療法案:本当に子どものためになっているのか?
2月に開催された緊急オンラインディスカッションでは、AIDで生まれた当事者や精子提供者らが、法案に対する意見を交わしました。このディスカッションは、自民・公明・維新・国民民主4党が提出した「特定生殖補助医療法案」を受けて開催されたものです。
法案の目的は、AIDで生まれた子の出自を知る権利の保障ですが、現行案には大きな問題点が2つあります。1つ目は、当事者の声を十分に聞かずに議論が進められ、真の出自を知る権利が保障されていないこと。2つ目は、生殖補助医療の対象が法律婚の夫婦に限定されていることです。
法案の要約と問題点
法案の要約は以下の通りです。
- 法律婚の夫婦のみが医療を受けられる。
- 提供者・受精卵提供を受けた夫婦・出生した子の情報は国立成育医療センターに100年間保存される。
- 出生した子は成人後、センターに以下のことを請求・要請できる。
- 情報保存の有無の確認
- 提供者の個人を特定しない情報の開示(身長、血液型、年齢など)
- センターを通して提供者へ特定できる情報の要請(提供者は拒否可能)
- 提供者死亡の場合、提供当時の同意があれば氏名の開示請求が可能
しかし、提供者には情報の開示を拒否する権利が認められており、生まれた子の出自を知る権利は十分に保障されているとは言えません。また、法律婚以外の夫婦が対象外となっている点も、多様な家族のあり方を無視しているとの批判があります。

出自を知る権利を求める声:アイデンティティの喪失と苦悩
日本では1948年からAIDが開始され、生まれた子は1万人以上と推定されています。しかし、親が子にAIDの事実を伝えないことが慣習化しており、出自を知った当事者はアイデンティティの喪失などに苦しむケースも少なくありません。
イギリス人男性の例では、生物学上の父親探しに多大な時間と精神的エネルギーを費やし、学生生活を十分に楽しめなかったと語っています。そして、ついに父親と会えた後、深い安堵感を覚えたといいます。
著名な家族心理学専門家である山田花子先生(仮名)は、「出自を知る権利は、個人のアイデンティティ形成に不可欠な要素であり、精神的な健康にも大きく影響する」と指摘しています。法案制定においては、当事者の声に真摯に耳を傾け、真の出自を知る権利を保障することが重要です。
まとめ:真の出自を知る権利の保障に向けて
提供精子・卵子による不妊治療は、子どもを望む夫婦にとって大きな希望となる一方、生まれた子の出自を知る権利という重要な課題も孕んでいます。現行の特定生殖補助医療法案は、当事者の思いを十分に反映しているとは言えず、さらなる議論が必要です。真に子どものためになる法整備に向けて、社会全体で真剣に考えていく必要があるでしょう。