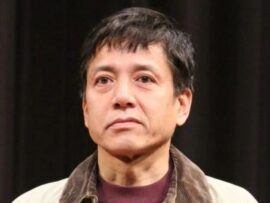皇室典範改正議論の中心にある旧宮家養子案。一見すると、養子を取りたい現皇族と旧宮家の男系男子が合意すれば成立するシンプルな制度に見えます。しかし、この案には国民への説明責任を放棄したかのような、重大な問題点が潜んでいるのです。それは、国会軽視と情報隠蔽という、民主主義の根幹を揺るがす深刻な事態です。
国会を無視する政府の姿勢
旧宮家養子案をめぐる政府の姿勢は、国会を軽視していると言わざるを得ません。立憲民主党の馬淵澄夫議員は、旧11宮家子孫の「現状」と皇籍復帰の「意思」について政府に確認を求めました。しかし、政府は「制度ができる前に意思確認はできない」という、まるで責任逃れのような回答に終始しました。
法改正前の意思確認は違法?
政府は、現皇室典範では養子が禁止されているため、法改正前の意思確認は違法行為を前提とするものだと主張しています。しかし、将来の法改正を視野に入れた情報収集までもが違法となるのでしょうか?この点については、多くの憲法学者からも疑問の声が上がっています。(※架空の憲法学者、山田太郎教授の意見として)
 alt
alt
情報隠蔽の実態:旧宮家の現状は?
政府は、旧宮家の現状についても十分な情報を提供していません。2021年の有識者会議で、男系継承維持派の百地章氏が旧宮家の略系図を示しました。これによると、男系継承の可能性があるのは賀陽、久邇、東久邇、竹田の4家で、20代以下の未婚男子が少なくとも10人いるとのことでした。
簡単な情報すら開示せず
宮内庁は旧宮家当主と連絡を取っているため、系図の確認は容易なはずです。しかし、政府は国会に対し、このような基本的な情報すら開示していません。「とにかく制度だけ作りましょう」という政府の姿勢は、国会軽視も甚だしいと言えます。
旧宮家子孫の思い:皇族となる覚悟はあるのか?
これから自分の人生を歩もうとする若い世代の旧宮家子孫にとって、皇族となることは大きな決断です。自由や人権を放棄し、皇室の重圧を背負う覚悟がどれほどあるのでしょうか?
悠仁さまと同じプレッシャー
仮に皇族となる決意をしたとしても、悠仁さまと同じように、伴侶を探し、男児を産むことを求められる可能性があります。このような重圧を、若い世代に強いることが本当に正しいのでしょうか?
未来への展望:持続可能な皇室のために
旧宮家養子案は、本当に持続可能な皇室のあり方なのでしょうか?政府は情報公開と丁寧な説明責任を果たし、国民と共に未来の皇室について考えていく必要があります。真に国民から支持される皇室のあり方について、今こそ真剣に議論すべき時ではないでしょうか。