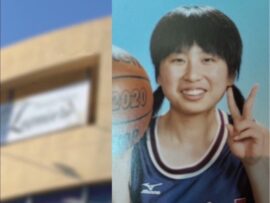陸上自衛隊の精鋭部隊、レンジャー。その過酷な養成訓練が、今年度をもって一部部隊を除き中止されることになりました。現代戦への対応力強化のための教育内容見直しという表向きの理由の裏には、訓練中の事故続発という深刻な問題が潜んでいるようです。今回は、元レンジャー隊員へのインタビューを基に、その過酷な訓練の実態と中止の真相に迫ります。
レンジャー養成訓練:憧れと現実の狭間
元レンジャー隊員の前田健太さん(仮名)は、ヘリコプターからのロープ降下など、高度な訓練をこなすレンジャー隊員の姿に憧れを抱き、厳しい訓練に挑みました。当時、レンジャーの資格を取得しても待遇に変化はありませんでしたが、約6000人の部隊から毎年100人弱の志願者が集まり、選抜試験を経て30人ほどの候補生が選ばれていたといいます。
 元レンジャー隊員の前田健太さん(仮名)
元レンジャー隊員の前田健太さん(仮名)
想像を絶する行動訓練:極限状態でのサバイバル
約3ヶ月に及ぶレンジャー養成訓練は、基礎訓練を経て、ゲリラコマンドの技術を学ぶ行動訓練へと移行します。行動訓練は約1ヶ月間、常に戦場にいるという想定下で行われ、不眠不休で山の中などでの任務に臨みます。50キロの装具を背負い、50キロの道のりを3夜4日歩き続けることもあるといいます。
食料確保:ヘビやカエルを食す
補給物資が来ない状況を想定し、ヘビやカエルなどの捕獲・調理方法も学びます。銃剣で叩いて平たく伸ばしたヘビを素焼きにして食べた前田さんは、「生臭い鮭とばのような味だった」と振り返ります。
水分制限:渇きとの戦い
過酷な訓練の中でも、特に耐え難かったのは水分摂取の制限だったと前田さんは語ります。「喉がカラカラに乾いているのに、ペットボトルのキャップ2杯までしか飲めない。雪を食べてお腹を壊したり、中には自分の尿を飲んでしまう隊員もいた」と、当時の壮絶な状況を明かしました。
精神的苦痛:仲間の脱落
肉体的・精神的な限界に達し、泣きながら訓練中止を懇願する隊員もいれば、プライドから崖から落ちるなど、自ら大怪我をして訓練を離脱する隊員もいたといいます。「根性なしと思われたくない」という思いが、さらなる悲劇を生んでいたのです。
レンジャー訓練中止の背景
約30人の候補生からレンジャー隊員になれるのは7割程度。大量の脱落者が出る年もあり、5人しか残らなかった年もあったといいます。こうした過酷な訓練の実態と、訓練中の事故続発を受け、陸上幕僚長は安全管理の徹底を理由に訓練内容の見直しを表明しました。
レンジャー訓練の未来:改革への期待
過酷なレンジャー訓練は中止となりますが、隊員の安全を確保しつつ、現代戦に対応できる新たな訓練内容への期待が高まります。「食料確保訓練の様子」を想像してみてください。過酷な環境下で生き抜くための知恵と技術を習得する隊員たちの姿が目に浮かびます。 著名な軍事評論家、加藤一郎氏(仮名)は、「レンジャー隊員の育成は国防上重要だが、時代に合わせて訓練内容を柔軟に見直していく必要がある」と指摘しています。 今後の自衛隊の精鋭部隊育成に注目が集まります。