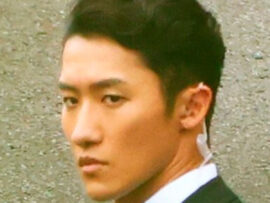近年、自閉症スペクトラム障害(ASD)への理解が深まりつつありますが、子どもたちの自立を支援する療育の重要性はますます高まっています。この記事では、2025年2月に83歳で逝去された河島淳子医師の生涯と、彼女が築き上げた独自の療育法についてご紹介します。河島医師は、長年にわたり自閉症児の療育に尽力し、多くの画家やアスリートを育て上げたパイオニアとして知られています。
河島医師の療育法とは? 生涯を捧げた情熱
河島淳子医師の療育法は、映画化もされ、檀ふみさんによってその生涯が演じられました。映画では、自閉症の画家として活躍する石村嘉成さんを育てたエピソードが描かれており、公開以来、河島医師の療育法に注目が集まっています。
 河島淳子医師の療育風景
河島淳子医師の療育風景
療育の原点は自身の経験
河島医師が療育の道を選んだ背景には、自身の経験がありました。彼女が約30年前に設立した愛媛県新居浜市の「トモニ療育センター」は、全国から800人以上の発達障害児とその家族を受け入れてきました。
具体的な療育方法:指示の徹底と社会性の育成
河島医師の療育法の中核を成すのは、「指示が通ること」の重視です。自閉症は脳機能の特性であり、特有の学びにくさがあるため、言葉や知的発達、運動機能の遅れにつながりやすいとされています。そして、適切な療育を受けなければ、社会性の発達が難しくなる可能性があります。
河島医師は、記録カメラの前で指示を出し、副所長が子どもを指導する様子を記録に残すなど、療育の様子を細かく分析していました。例えば、2歳で自閉症と診断された5歳の男の子に対しては、じっと座っていられないという課題に対し、指示を理解し行動に移せるよう、根気強く指導していました。
社会性の第一歩
河島医師は、「指示が通ることが社会性の第一歩」と述べています。親の指示に従うことができるようになることが、社会生活を送る上で非常に重要だと考えていました。
河島医師の功績と未来への展望
河島医師の療育法は、自閉症児の自立を支援する上で大きな役割を果たしてきました。彼女が残した功績は、多くの関係者に感銘を与え、今後の療育の在り方にも影響を与えていくことでしょう。
言葉と運動の指導で生きづらさを解消
河島医師は、言葉や運動を教えることで、自閉症に伴う生きづらさを解消できると考えていました。療育を通じて、子どもたちが社会で活躍できるよう、可能性を広げるためのサポートを続けました。
まとめ:未来を担う子どもたちのために
河島淳子医師は、自閉症療育の分野において先駆的な役割を果たし、多くの子供たちの未来を切り開いてきました。彼女の功績を振り返り、今後の療育の更なる発展に期待したいと思います。