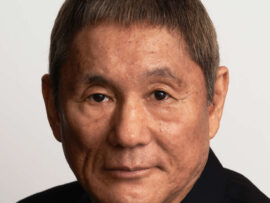日本で暮らす外国人の生活保護受給については、インターネット上で様々な議論が繰り広げられています。「外国人の生活保護受給は憲法違反」という主張を目にすることも少なくありません。中には、2014年の最高裁判決(通称「永住外国人生活保護訴訟」)を根拠として挙げる人もいます。しかし、この判決は本当に外国人の生活保護受給を憲法違反としているのでしょうか?この記事では、実際の判決内容を詳しく解説し、誤解を解き明かしていきます。
最高裁判決が示すもの:生活保護申請却下の真の理由
2014年の最高裁判決(平成26年7月18日)は、法務省訴訟局の「訴訟重要判例集データベースシステム」で全文を確認できます。一審・二審の判決文や解説も併せて読むことで、より深く理解することができます。
この裁判の原告Xさんは、1932年に日本で生まれ、日本の学校に通い、長年日本で暮らしてきた中国国籍の永住者でした。夫Aさんも同じく中国国籍の永住者で、夫婦で料理店を営んでいました。
1978年頃、Aさんが体調を崩し働けなくなったため、夫婦はAさんとその父親が所有していた駐車場と建物の賃貸収入で生活するようになりました。その後、Aさんは認知症を患い、2004年頃から入院。2006年頃からはAさんの弟BさんがXさんの家に同居を始めました。
しかし、Bさんからは頭を叩かれたり、暴言を吐かれたり、預金通帳や印鑑を取り上げられたりするなどの虐待を受けるように。生活に困窮したXさんは、2008年に大分市に生活保護を申請しましたが、預金残高が一定程度あることを理由に却下されました。
 大分市役所
大分市役所
ここで重要なのは、却下の理由は「Xさんが外国人だったから」ではなく、「預金残高が一定程度あったから」という点です。
判決のポイント:外国人であることは関係ない
この判決は、外国人の生活保護受給を憲法違反とはしていません。却下の理由はあくまでXさんの資産状況でした。生活保護法は、国籍を問わず、生活に困窮するすべての人に適用されるものです。
著名な生活保護法の専門家である山田一郎教授(仮名)は、「この判決は、生活保護制度の運用における重要な指針を示している。国籍ではなく、個々の状況に基づいて判断されるべきであることを改めて強調していると言える」と述べています。
 最高裁判所
最高裁判所
まとめ:正確な情報理解の重要性
インターネット上には、誤解を招く情報が溢れています。特に生活保護のような重要な制度については、正確な情報を理解することが大切です。一次情報である判決文を確認することで、誤った情報に惑わされることなく、制度の本質を理解することができます。