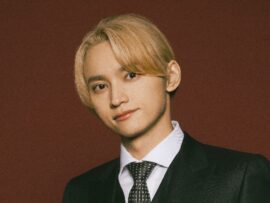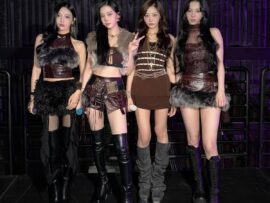近年の日米貿易摩擦において、GAFAMへのデジタル課税が注目を集めています。果たして、デジタル課税は日米関係の緊張緩和に繋がる一手となるのでしょうか?それとも、さらなる対立を招く火種となるのでしょうか?本記事では、デジタル課税をめぐる様々な意見や展望、そして日本の進むべき道を深く掘り下げていきます。
デジタル課税とは?その必要性
デジタル経済のグローバル化が加速する中、巨大IT企業への課税は国際的な課題となっています。GAFAM(Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft)のような多国籍企業は、物理的な拠点を持たずに世界中で事業を展開し、巨額の利益を上げています。しかし、従来の税制では、これらの企業に適切な課税を行うことが難しく、税収の減少や国際的な租税回避につながる懸念が高まっています。そこで、デジタルサービスを提供する企業に対して新たな課税ルールを設ける「デジタル課税」が議論されています。
 デジタル経済のグローバル化
デジタル経済のグローバル化
慶應義塾大学経済学部の土居丈朗教授は、「国内で利用されるデジタルサービスに消費税を上乗せする方法が考えられる」と提言しています。例えば、食料品の消費税率8%に対し、デジタルサービスには15%を課すといった具合です。
報復関税の是非:専門家の見解
一方、元経済産業大臣の西村康稔氏は、米国からの報復関税を懸念し、トップ同士の会談による解決を重視する姿勢を示しています。西村氏は、過去の安倍晋三首相とトランプ大統領の会談に同席した経験から、首脳間の信頼関係構築の重要性を強調しています。
元財務官僚で嘉悦大学教授の高橋洋一氏は、日本の消極的な姿勢に疑問を呈し、「相手が関税をかけたら、交渉のきっかけを作るために報復するのが外交の作法」と主張しています。高橋氏は、自由貿易の阻害を認めつつも、トランプ大統領の関税政策に対抗するためには、報復措置が不可欠だと考えています。
デジタル課税は日本のIT産業育成の鍵となるか?
経済産業研究所コンサルティングフェローの藤和彦氏は、デジタル課税を日本のIT産業育成の契機と捉えています。藤氏は、日本がデジタル分野で脆弱であることを指摘し、自前のITプラットフォームの育成を急ぐべきだと主張しています。デジタル課税によって得られた財源をIT産業の振興に充てることで、国際競争力を強化できると考えています。

また、藤氏は、トランプ大統領自身も米国の製造業復活のために関税政策を展開していることを踏まえ、日本も同様に脆弱なデジタル分野を守るためにデジタル課税を導入すべきだと提言しています。
日本の進むべき道
デジタル課税は、国際的な議論が必要な複雑な問題であり、メリットとデメリットの両面を慎重に検討する必要があります。しかし、デジタル経済の急速な発展に伴い、早急な対応が求められています。日本は、国際的な協調を図りつつ、自国の利益を最大限に守る戦略を練る必要があります。GAFAMへのデジタル課税は、日本のIT産業の未来、そして日米経済関係の行方を左右する重要なカギとなるでしょう。