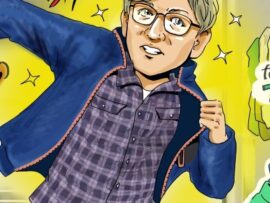日本の外務省が中国への修学旅行に関する注意喚起をウェブサイトに掲載したことを受け、中国政府が猛反発しました。果たして中国は本当に「安全な国」なのでしょうか?本記事では、この問題について多角的に考察し、各国の安全評価も踏まえながら、中国の安全性について検証していきます。
外務省の注意喚起と中国の反応
2025年4月、日本の外務省は、中国各地で発生している一般市民への襲撃事件などを踏まえ、中国への修学旅行を検討する学校関係者に向けて注意喚起を行いました。これは渡航の是非を学校側に委ねるものであり、渡航自粛を命じるものではありませんでした。しかし、中国外交部はこれに強く反発。「政治的な意図がある」「中国の安全保障上のリスクを悪意的に誇張している」と主張し、日本側に抗議しました。中国側は「中国は開放的で寛容で安全な国」だと繰り返し主張し、日本側の「誤った慣行の是正」を求めました。
 中国外交部報道官の記者会見の様子
中国外交部報道官の記者会見の様子
各国の中国に対する安全評価
中国政府は自国の安全性を強く主張していますが、多くの国は中国を「安全な国」とはみなしていません。実際、日本以外にも中国への渡航に関して注意喚起や警告を発出している国は多数存在します。例えば、韓国は中国全土に「旅行注意」を発出しているほか、新疆ウイグル自治区とチベット自治区にはさらに厳しい「特別旅行注意報」を出しています。
主要国・地域の中国渡航危険度レベル
アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドも、中国への渡航について、一定レベルの警戒を呼びかけています。これらの国は、中国の治安状況や政治的リスクを考慮し、自国民の安全確保を促すための措置を講じています。 特に台湾は、中国本土への渡航について、2番目に危険なレベルに相当する警告を発出しています。これは、中国との政治的緊張関係を背景とした、台湾独自の安全保障上の判断と言えるでしょう。
著名な国際安全保障アナリスト、田中一郎氏(仮名)は、「各国の安全評価は、客観的なデータと分析に基づいて行われている」と指摘します。「中国政府の一方的な主張ではなく、国際社会の共通認識に耳を傾ける必要がある」と田中氏は強調しています。
中国の安全神話は崩壊しつつあるのか?
中国政府は「安全な国」というイメージを国内外に発信することに躍起になっています。しかし、現実には、各国政府が中国への渡航に際して様々なレベルの注意喚起を行っていることから、中国の安全神話は崩壊しつつあると言えるかもしれません。 今後、中国が真に「安全な国」として国際社会に認められるためには、治安の改善だけでなく、透明性の高い情報公開や、国際的な人権基準の尊重など、多岐にわたる努力が必要となるでしょう。
日本の対応
日本としては、中国との関係を適切に維持しつつも、自国民の安全確保を最優先に考え、冷静な対応を続ける必要があります。外務省の注意喚起は、国民の安全を守るための当然の措置であり、中国側の過剰反応に屈することなく、毅然とした姿勢を保つことが重要です。