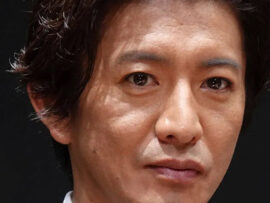祇園祭が終わり、学生街でもある京都は本格的な夏を迎えます。猛暑が続く中、今年は例年よりセミの声が少なく感じられますが、古都の夜にはさまざまな妖怪たちがその姿を現します。伝統的な「百鬼夜行」から、現代にも語り継がれる“物の怪”まで、京都に息づく不思議な存在たちを通じて、暑い夏の夜を涼やかに、そして奥深く探訪してみませんか。
千年の都に息づく「物の怪」の系譜
夜、一人で向かうトイレが怖かったのは、そこに漆黒の闇が広がっていたからかもしれません。水木しげる氏の漫画に登場する目玉おやじ、子泣きじじい、砂かけばばあ、ねずみ男、ネコ娘、一反もめん、そして鬼太郎といったキャラクターたちは、妖怪たちに親しみやすいイメージを与えました。しかし、千年以上の歴史を持つ京都の都は、恐ろしい怨霊や、夜に群れをなす百鬼夜行など、見る者の心胆を凍らせる「物の怪」に満ちています。
『源氏物語』では、光源氏が慕う夕顔や、正妻である葵の上への嫉妬に駆られた六条御息所が「もののけ(生霊)」となり、二人に取り憑き、ついには死に至らしめたとされています。嫉妬や無念な思いは、時に人を鬼や怨霊へと変貌させてしまう、と古くから信じられてきました。
都を震わせた最強の怨霊:菅原道真公
京都の怨霊の中で、多くの人々が一致して「最強」と認めるのは、政争に巻き込まれて大宰府へ左遷され、不遇の死を遂げた菅原道真公(903年没)でしょう。その計り知れない無念は都の人々から「怨霊」として恐れられ、鎮魂のために947年(天暦元年)には北野天満宮(上京区)が創建されたほどです。『北野天神縁起絵巻』には、その怨霊が引き起こしたとされる出来事が描かれており、一度は目にする価値があります。道真公を祀る天満宮は全国に1万2000社以上(諸説あり)あると言われ、学問の神様として今もなお厚い信仰を集めています。
北野天満宮では、8月2日から17日まで、無病息災を祈願する「北野七夕祭」が開催されます。境内を流れる御手洗川に足を浸す「足つけ燈明神事」のほか、夜には七夕飾りと提灯が幻想的に彩る「北野萬燈会」も行われます。期間中に巡るなら、国宝に指定されている御本殿石の間通り抜け神事(8月8日~11日)にも注目です。受験直前ではなく、夏の学習期間中に、学業成就や合格を祈願するのも良いでしょう。
疫病退散を願った「鬼」の姿:慈恵大師良源
4年にわたる新型コロナウイルス禍の記憶が薄れつつありますが、歴史上、疫病の蔓延は常に都の人々を苦しめてきました。自身の姿を鏡に映し、疫病退散を念じた結果、骨と皮ばかりの「鬼」のような姿になってしまったと伝えられるのが、比叡山延暦寺の中興の祖として知られる慈恵大師良源です。彼の弟子がその姿を版木に写し取り、お札として世に広めたところ、疫病のパンデミックが鎮まったと言われています。良源は1月3日生まれであることから「元三大師(がんざんだいし)」とも呼ばれ、比叡山延暦寺をはじめとする天台宗の寺院では毎月3日が縁日となっています。ぜひ「角大師(つのだいし)」と呼ばれるお札を授かり、厄除けと健康を祈願してみてはいかがでしょうか。
 真夏の京都の夜を彩る高台寺のプロジェクションマッピング、妖怪の姿も
真夏の京都の夜を彩る高台寺のプロジェクションマッピング、妖怪の姿も
伝説の鬼と蜘蛛:京都を騒がせた異形たち
京都に伝わる鬼の伝説といえば、「酒呑童子(しゅてんどうじ)」を忘れてはなりません。彼は都に現れては金銀財宝を奪い、女性や子どもを攫う、まさに手に負えない存在でした。一条天皇の命を受けた源頼光(みなもとのよりみつ)は、家来である四天王(渡辺綱、坂田金時、卜部季武、碓井貞光)を率いて、酒呑童子の討伐のため丹波国の大江山へと向かいます。頼光たちは酒を飲ませて酔いつぶれた鬼たちを斬り、その首を都へ持ち帰ろうとしますが、首は次第に重さを増し、結局大江山の麓に埋めたという伝説が残されています。
秋には、その大江山で「大江山酒呑童子祭り」(福知山市)が開催され、伝説の舞台を訪れることができます。また、源頼光が土蜘蛛(つちぐも)に襲われ、伝家の宝刀「膝丸(ひざまる)」(ゲーム「刀剣乱舞」でも有名になりました)で撃退したという伝説ゆかりの場所も、京都には存在します。一つは北野天満宮の南に隣接する東向観音寺(上京区)にある「土蜘蛛塚の灯籠」、もう一つは船岡山に近い紫野の上品蓮台寺(北区)にある「源頼光朝臣塚」です。北野天満宮の七夕祭と合わせて、これらの神秘的な場所を巡ることで、京都の奥深い歴史と伝説に触れることができるでしょう。
夏の京都で感じる非日常
夏の京都は、日中の厳しい暑さとは裏腹に、夜になると古くからの言い伝えや伝説が息づく神秘的な表情を見せます。今回ご紹介した妖怪や怨霊の物語は、単なる怖い話ではなく、人々の感情や歴史、そして自然への畏敬の念が形になったものです。これらの物語を辿る旅は、千年の都が持つ奥深い魅力を再発見し、猛暑の夏を涼やかに、そして知的に過ごすための特別な体験となるでしょう。ぜひ、この夏は京都に潜む「怪異」を訪ね、非日常の世界に足を踏み入れてみてください。
参考資料
- ダイヤモンド・ライフ編集部, らくたび. (2024, July 31). 真夏の京都の妖怪はこんな姿! [記事]. Yahoo!ニュース. https://news.yahoo.co.jp/articles/161e15d52b1d58e1bade31a7e92430c1bcd05e62