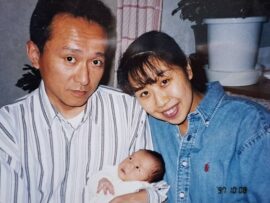7月25日に「大自然没入型テーマパーク」として鳴り物入りでオープンしたばかりの「ジャングリア沖縄」が、早くも各方面から厳しい声に晒されています。新しいテーマパークが賛否両論に直面することは珍しくありませんが、2017年に開業した「レゴランド・ジャパン」の時以上に、今回は辛辣な意見が目立ちます。特に、事前プロモーションが膨らませた期待値と実際の体験との間に大きな隔たりがあることが、批判の主要な原因として指摘されています。
 ジャングリア沖縄の外観とコンセプトを示すイメージ(開幕直後から批判に直面)
ジャングリア沖縄の外観とコンセプトを示すイメージ(開幕直後から批判に直面)
SNSでの辛辣な声:CMとのギャップ
実際にジャングリア沖縄を訪れた来場者のSNS上では、「子どもは楽しめるが、大人は物足りない」「CMと実物のアトラクションにギャップがある」といった批判が多数投稿されています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)を彷彿とさせるようなテレビCMで期待値が高まっていただけに、来場者は「思っていたのと違う」と落胆しているようです。テレビCMが描いたドラマチックな体験と実際の提供内容との乖離が、来場者の満足度を大きく左右しています。
 ジャングリア沖縄で楽しめるアトラクションの一例(期待と現実のギャップの一因)
ジャングリア沖縄で楽しめるアトラクションの一例(期待と現実のギャップの一因)
専門家からの厳しい指摘:「アトラクション不足」と「失敗」の予言
一般の来場者だけでなく、テーマパーク業界の専門家からもジャングリア沖縄に対しては厳しい見解が示されています。日本遊園地学会の塩地優会長は、ジャングリア沖縄の全22アトラクション中「テーマパークらしいのは3つほど」と厳しく評価。さらに、「最初の1ヶ月は100万人ペースでも、その後は大きく来場者が減り『失敗』するだろう」と予言しています(現代ビジネス 2025年7月4日付「《ガラガラになる可能性も》「類似の施設が多すぎ」…専門家が「ジャングリア沖縄」の失敗を断言できるワケ」より)。この指摘は、施設の根幹であるアトラクションの質と数への懸念を示唆しています。
「大自然没入型」のコンセプトと現実の乖離
ジャングリア沖縄への批判の背景には、そのコンセプトである「大自然没入型テーマパーク」と実際の体験との乖離も指摘されます。沖縄北部に広がる約60ヘクタールの雄大な「やんばるの森」という本物の自然の中に位置している点は、そのキャッチコピーに偽りはありません。しかし、その広大な自然の中に足を踏み入れると、来場者を迎えるのは「コテコテの人工物」であるリアルな恐竜ロボットです。
恐竜が大好きな子どもたちにとっては、このロボットたちは大興奮の対象となるでしょう。しかし、ある程度の年齢層の若者や、恐竜に特に関心のない層からすれば、「よくできた作り物だね」という程度の感想に留まりがちです。せっかくの雄大な大自然の中に身を置いているにもかかわらず、精巧な恐竜ロボットという「人工的な創造物」が中心となることで、本来謳われるべき「大自然への没入感」が薄れてしまう、という皮肉な状況が生まれています。
テーマパークにおけるロボットや精巧なセットは、通常、ディズニーランドの定番アトラクション「カリブの海賊」のように「日常を忘れさせてくれる閉ざされた空間」の中でこそ、その没入感を最大限に発揮します。開放的な大自然の中に「人工の驚き」を配置する際、そのバランスや演出が極めて重要となることが、ジャングリア沖縄の事例から浮き彫りになっています。
まとめ
ジャングリア沖縄への批判は、広告によって高まった期待値と実体験のギャップ、アトラクションの種類と数に対する専門家の懸念、そして「大自然没入型」という独自のコンセプトと、園内に設置された人工物との間の乖離という、複数の要因が複合的に絡み合って生じています。沖縄の豊かな自然を最大限に活かしつつ、来場者が真に「没入」できる体験を提供するためには、今後、コンセプトとアトラクションの整合性をどのように図っていくかが、ジャングリア沖縄にとっての大きな課題となるでしょう。今後の動向が注目されます。
Source: Yahoo!ニュース