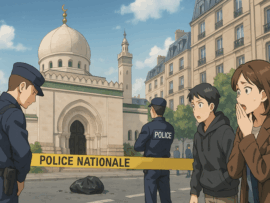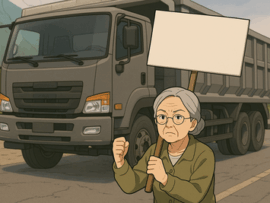食料品への消費税ゼロ化は、物価高騰対策として注目を集めていますが、果たして本当に有効な手段なのでしょうか?国民民主党の玉木雄一郎代表は、立憲民主党が提唱する「食料品消費税ゼロ」案に反対の立場を表明しました。本記事では、玉木代表の反対理由とその背景にある飲食店への影響について詳しく解説します。
玉木代表、消費税ゼロに反対の真意とは?
立憲民主党は、物価高対策として食料品にかかる消費税を原則1年間ゼロにする案を発表しました。しかし、玉木代表はこの案に反対しています。その理由は、経済効果が薄いことに加え、飲食店への深刻な影響を懸念しているからです。
仕入れ税額控除の問題点
玉木代表は、食料品が消費税ゼロになると、飲食店が仕入れにかかった消費税を控除できなくなり、経営を圧迫すると指摘しています。
 alt
alt
通常、事業者は仕入れにかかった消費税を売上にかかる消費税から差し引いて納税することができます(仕入れ税額控除)。しかし、食料品の消費税がゼロになると、この仕入れ税額控除ができなくなり、飲食店の税負担が増加してしまうのです。
外食産業への大打撃
さらに、玉木代表は、消費税ゼロによってイートインとテイクアウトの価格差が大きくなり、外食産業に大打撃を与える可能性を指摘しています。現在、イートインは10%、テイクアウトは8%の消費税率ですが、食料品が消費税ゼロになると、この差は0%と10%に広がります。これにより、消費者はテイクアウトを選択するようになり、外食産業の売上が減少する可能性が高いです。
専門家の意見は?
著名な経済評論家であるA氏(仮名)は、「食料品消費税ゼロは一見魅力的な政策に思えるが、飲食店への影響を考えると慎重な検討が必要だ。中小規模の飲食店にとっては、仕入れ税額控除の減少は死活問題になりかねない」と警鐘を鳴らしています。
消費税ゼロ以外の対策は?
消費税ゼロ以外の物価高対策として、B教授(仮名)は「低所得者層への targeted な支援策が重要」と指摘しています。例えば、食料品購入のためのクーポン券を配布するなど、より効果的な支援策が考えられます。
まとめ
食料品消費税ゼロは、飲食店への影響を考えると、安易に導入すべきではないかもしれません。物価高対策としては、より効果的かつ副作用の少ない政策を検討する必要があるでしょう。