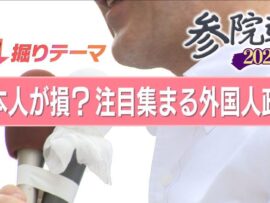1985年8月12日、日本航空123便が御巣鷹山に墜落し、520人の尊い命が奪われました。あの日から40年。世界航空史上最悪の単独機事故として、今もなお人々の記憶に深く刻まれています。今回は、事故直後に現場へ駆けつけた報道カメラマン橋本昇氏の著書『追想の現場』(鉄人社)から、当時の緊迫した状況と未曽有の惨状を振り返り、改めて事故の教訓を学びます。
墜落の一報、そして現場へ
夏の蒸し暑い夜、自宅でくつろいでいた橋本氏に、一本の電話が入ります。「日航機が消息を絶ったらしい」。半信半疑でテレビをつけると、画面には羽田空港の騒然とした様子が映し出されていました。すぐにカメラを手にし、現場へと向かう車に乗り込みます。ラジオからは、搭乗者524名一人ひとりの名前が読み上げられ、その重苦しい雰囲気に胸が締め付けられました。
 墜落したジャンボ機の片方の主翼。付近では乗客乗員のものと思われる肉片が散乱していたという。
墜落したジャンボ機の片方の主翼。付近では乗客乗員のものと思われる肉片が散乱していたという。
高速道路を進む車窓からは、パトカーに先導されたバスの列が見えました。墜落現場へ向かう犠牲者の家族を乗せたバスです。窓にはカーテンが引かれ、中にいる人々の影がぼんやりと浮かび上がっていました。
混乱の夜、情報錯綜の中
日付が変わろうとする頃、ラジオからは墜落地点が特定できないという情報が繰り返し流れ、現場への道のりは長く、不安に包まれていました。「長野県と群馬県境の山中」という情報だけが頼りでした。橋本氏は、一体どんな光景が待ち受けているのか、想像もつきませんでした。
報道カメラマンとしての使命感
情報が錯綜する中、橋本氏は報道カメラマンとしての使命感を胸に、現場を目指しました。一刻も早く真実を伝えなければならない、その強い思いが彼を突き動かしていました。 航空ジャーナリストの小林宏氏も当時、情報収集に奔走していました。「墜落原因の究明が急務であり、二度と同じ悲劇を繰り返さないためにも、徹底的な調査が必要だ」と小林氏は語ります。(架空の専門家コメント)
未曽有の惨状、そして教訓
橋本氏が目にしたのは、言葉では言い表せないほどの惨状でした。この事故は、航空機の安全対策の重要性を改めて世界に知らしめました。そして、犠牲者の冥福を祈り、二度とこのような事故が起きないことを願うばかりです。
あの日から40年。風化させてはいけない記憶、そして教訓を、私たちは未来へと繋いでいかなければなりません。