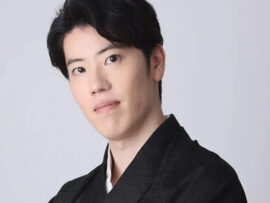昨今の少子化は若者の婚姻減によるもの。そして、若者の婚姻減は決して「若者の恋愛離れ」などという価値観も問題ではないことも明白です。
【画像でわかる】「恋愛弱者」や「経済弱者」は結婚できないのか?
若者の「恋人のいる割合」というのは、出生動向基本調査の長期推移を見ても明らかなように、令和の今も40年前の昭和もほぼ3割程度で変化はありません。「高校生のデート未経験率4割」などが話題になったことがありましたが、それも40年前の高校生とほぼ一緒です(参照→景気によって「若者の恋愛観変わる?」意外な事実)。
「若者が結婚する意欲を失ったからだ」などという論も間違いです。これも出生動向基本調査で1992年から2021年まで20〜30代の独身男女の「結婚前向き率」は、男4割、女5割でまったくといっていいほど変化はありません(参照→日本の若者「本当は結婚したい」のにできない真因)。
つまり、婚姻が減ったのは若者の恋愛力の低下や結婚意欲の減退などではないということです。
■若者の婚姻数がここ10年間で急激に減った理由
では、なぜ若者の婚姻数が減ったかといえば、それは20〜30代の中間層年収帯の婚姻が減ったことがすべてです。それも、ここ10年間で急激に。
内閣府の国民生活基礎調査より、20〜30代世帯主の児童のいる世帯の数は、2003年から2013年の10年間ではほぼ減ってはいません。が、2013年から2023年の10年間で約50%減です。
しかも、世帯年収別に増減を見ると、年収300万円未満では55%減、年収300〜500万円の中間層帯では66%減です。500万円以上では38%減にとどまっていることから、人口ボリュームの多い中間層の若者の結婚と出産が特に減っていることを示しています。
ちなみに、世帯年収900万円以上では逆に14%も増えています。要するに、これだけ婚姻や出生が減っているとはいえ、経済上位層はまったく減っていないわけです。
企業規模別の未婚率の増減も確認しておきましょう。就業構造基本調査より企業規模別の男性35〜39歳の未婚率増減を2012年と2022年で比較すると、中小企業6%ポイント増であるのに対し、大企業はわずか1%ポイント増、官公庁はむしろ▲3%ポイント減という状況です。