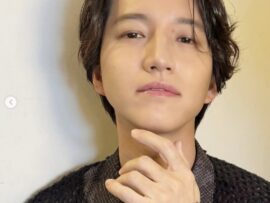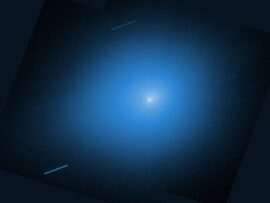奨学金制度は、進学の機会を与える一方で、当然ながら卒業後には長期にわたる返済義務が生じる。特に経済的な不安を抱える家庭にとってこの返済は、大きな足かせとなり、子どもの進学にも影響を与えかねない。本記事では、シングルマザーAさんの事例とともに、奨学金の支援措置について、アクティブアンドカンパニー代表の大野順也氏が解説する。
シングルマザーの経済的重圧と子育ての両立
Aさんは現在44歳。関東地方で3人の子どもを育てるシングルマザーである。3番目の子どもが生まれて間もなく、夫の不倫が原因で離婚。養育費は支払われず、一人で生計を立てるなか、大学時代に借りていた奨学金の返済が毎月約2万7,000円と、家計に重くのしかかっていた。
3番目の子どもが幼稚園に入園するまではフルタイムで働くことが難しく、業務委託で稼いだ月16万円程度の収入でやりくりする日々。児童手当を頼りに、なんとか生活を維持していたものの、経済的な厳しさから実家に戻ることも考えた。しかし、両親は弟夫婦と同居していることから気兼ねし断念。実家までは車で2時間かかるため、頻繁に子どもを預けることも難しかった。
返還期限猶予という選択
3番目の子どもが幼稚園に入園するタイミングで、Aさんの経済状況は限界に達し、日本学生支援機構(以下、JASSO)の「返還期限猶予」という救済措置を利用して、一時的に奨学金の返済を止める決断をした。この制度は、経済困難などの理由がある場合に返済を猶予してもらえる制度だが、返済義務が消滅するわけではなく、猶予期間が終了すれば再び返済が始まる。一時的な先送りに過ぎないことには注意が必要だ。
終わらない奨学金返済と新たな借金
3番目の子どもが小学校に入学したのを機に、Aさんは正社員として職場に復帰。収入は安定したものの、それまでの生活で貯金はほとんど残っていなかった。
そして、長男が高校に進学する時期を迎え、塾の費用や将来の大学進学にかかる費用を調べて、その金額の大きさに衝撃を受けた。自身の収入だけでは到底賄えないと考えたAさんは、子どもにも自分と同じように奨学金を借りてもらうことを決めた。そしてこの春、長男が念願の大学に進学。しかし、入学金や初年度納入金の高さに直面し、さらに別のローンを組んで支払ったという。
大学時代の奨学金の貸与月額が10万円であったAさんは、当初の返済計画どおりであればいまの年齢には返済を終えているはずだった。しかし、返還猶予制度を利用した期間があるため、返済までにあと3年程度かかる見込みだ。さらに、長男の大学進学のためのローンの返済も加わることになる。完済年齢はAさんが68歳になるタイミングである。
それでも奨学金を借りてよかった
Aさんは、「末の子が小学校に入学したタイミングで正社員になれたことは本当に大きかった。あのときに正社員になれなかったら確実に路頭に迷っていた。いまの状況が苦しいのも奨学金の返済が大きな負担ではあるが、奨学金がなかったら私は大学にも行けず、子どもを3人抱えて超低収入のまま毎日次の日の生活費を心配しながら暮らしていたと思う。奨学金を借りてよかった。子ども全員を大学に入れてきちんと卒業させるまでは、なんとか頑張らなければならない」と笑顔で語る。
経済的な負担は非常に大きく、自身の老後のための貯蓄に対しての不安もあるというが、3人の子の母親としてAさんは強く逞しく生きている。