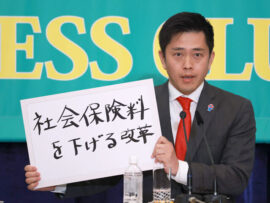NHK朝ドラ「あんぱん」で学校教師を目指している主人公・朝田のぶが学ぶ女子師範学校は「忠君愛国」を徹底して生徒たちに叩きこんでいる。のぶ自身は、そこに若干、微妙な反応を示していることもあるのだが、友人はいつの間にか完全に、そちら側の思考に染まっているようだ。
しかし数年後には、その教育が敗戦によって根底から否定されることになるのを視聴者はよく知っている。
その時、教えを信じ込んできた先生や友人たちはどうなるのか、のぶたちは正気でいられるのか――この先の展開を考えてハラハラしている方も多いことだろう。
現実の世界でも、昭和20年8月15日の経験が人生を左右したという人は少なくない。『バカの壁』で知られる養老孟司さんもその一人だ。東京大学医学部に進みながら、生きている人を診察するのではなく、解剖学の道に進んだことは、敗戦時の経験が大きく影響しているのだ、と新著『人生の壁』で明かしている。一体何があったのか。もう一つの理由と共に、養老さんの職業観が伝わってくる文章をご紹介しよう(以下、『人生の壁』より抜粋・引用しました)
***
世の中で確かなものとは何だろう
大学で解剖学をなぜ選んだか。世間で医者といえば、内科や外科、小児科等々をイメージする方が多いのは今も昔も同じです。解剖学は決してメジャーな存在ではありませんでした。
それでも解剖学の道に進んだ理由の一つは、「確実さ」があったからです。よくお話ししているように、小学校低学年の時に、敗戦によって世の中がひっくり返ってしまうのを目の当たりにしました。
昨日まで絶対に正しいとされていた教科書に、正しいことを教えていたはずの先生が墨を塗れと言う。大人の言っていることは全部嘘だった。言葉は信用できない。そんな経験をすると、「一体、世の中で確かなものとは何だろう」という問題を考えざるをえなくなります。
一方で自然は嘘をつきません。よくわからないことばかりだけれど、それは自然に問題があるわけではない。
そもそも理系を選んだのも、文系よりは確かな分野だろうという気持ちがありました。
医学部でも「確実さ」を求めていき、解剖学が一番確かなものではないかという結論に至ったわけです。
これは別に私だけの考えではありません。昭和20年卒業の細川宏先生という東大医学部の解剖学の先生は、「医学の中で一番確実な学問とは何かと考えたら、解剖学だという結論が出た。だから自分はこの道を選んだ」と仰っていました。
ここで言う「確実さ」とは、収入の安定とか、社会的な評価だとか、そういう類のこととは一切関係がありません。
むしろ、医学部を出て解剖学をやったところで、潰しはきかないのです。病院で勤務医として働くこともできないのですから。その意味で経済的な確実さは怪しい。
一応、どの医学部にも解剖学の講座があることはありましたが、基礎研究なので、ポストが十分にあるとも限りませんでした。
あくまでも学問として見た場合、いきなりひっくり返るようなことにはならない性質の分野だということです。
昨日までの一億玉砕本土決戦が、玉音放送の後は平和と民主主義にひっくり返った。そういうことが学問の世界でもあるのではないか。そんなことが真剣に気になる時代だったのです。