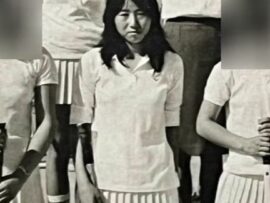元テレビ朝日社員の玉川徹氏が、20日投開票の参議院選挙を巡りSNS上で拡散される真偽不明な情報について、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で私見を述べ、その防止策に注目が集まっています。デマ情報が投票行動に影響を与えている現状に対し、言論の自由を尊重しつつも、SNS運営企業による積極的な対策と、それを後押しする法規制の必要性を強く訴えました。
溢れる虚偽情報と投票行動への影響
番組の恒例企画「参院選 あふれる真偽不明情報 切り抜きもそう確かめる?」では、参院選に関連する石破茂首相や小泉進次郎農相らに関する投稿が、実際には事実と異なる内容で拡散されている事例が紹介されました。真実とフェイク情報の見分け方や向き合い方について、有権者の声や専門家の意見を交えながら議論が展開されたのです。
玉川氏は、提示された虚偽情報を例に挙げ、「デタラメ情報であふれているのは事実。デタラメ情報で影響を受けて、投票行動に結びついているのも事実だ」と現状を明確に指摘。さらに、「このような空間を社会が容認して良いのか」と問題提起し、被害を防ぐための備えも重要だが、社会全体としてこの情報環境をどう位置づけるかまで議論が深まるべきだと訴えました。
 参院選に関するSNS虚偽情報について見解を述べる玉川徹氏。
参院選に関するSNS虚偽情報について見解を述べる玉川徹氏。
「言論の自由」とSNS運営企業の役割
日本の「言論の自由」は重要な原則であるとしつつも、玉川氏は「一定の『かせ』をはめるのは、日本の憲法のもとでも可能だと思う」と、言論の自由の範囲内で虚偽情報対策を講じることの妥当性を示唆しました。
具体的な対策として、玉川氏はSNSを運営する企業に焦点を当てました。「SNSは、運営企業が間違いと思えば削除できるし、間違い情報を出しているようなアカウントを凍結もできる」と述べ、当局が全体に規制をかけるのではなく、運営側が自主的に対策を講じるよう働きかけるべきだと主張しました。さらに、「(事実ではないと)通報があったら、SNS側が止める。最低限でも課金できないようにするのは必要だと思う」と、虚偽情報からの収益化阻止の重要性を強調しました。
経済的動機への対策とAI活用
約20年前であれば、自民党への批判的な情報は「反自民」という動機が考えられたが、現在は「バズればお金になる」という経済的動機で虚偽情報を拡散する者がいると玉川氏は指摘しました。こうした「お金にする」行為は阻止できるはずだとし、外部からの通報はもちろんのこと、SNS運営側が率先して対策を講じるべきだと訴えました。
「お金をかけてでも、社会に悪影響を与えることはSNS側で防いでいく。できるはずだ」と強く主張し、大手のSNS企業は豊富な資金を持つため、コストをかけて独自に情報チェックを行うべきだと述べました。さらに、AIを活用すれば、相当なレベルで虚偽情報を弾くことが可能であるとし、これらを法規制で義務付けることで、「言論の自由を守りながら、悪い空間を良い空間に変えていくことはできるのではないか」と私見を締めくくりました。
結論
玉川徹氏の今回の発言は、参議院選挙という重要な時期に際し、SNS上の真偽不明情報が社会に与える影響の大きさを改めて浮き彫りにしました。彼の提言は、日本の「言論の自由」を尊重しつつも、SNS運営企業の社会的責任と、最新の技術(AIなど)を用いた情報管理の強化、さらにはそれを後押しする法的な枠組みの必要性を示唆しています。健全な情報環境を構築するためには、プラットフォーム側の主体的な取り組みと、それを促す社会全体の意識向上が不可欠であると言えるでしょう。
参考文献: