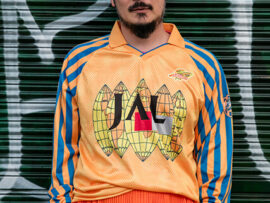(CNN) 5億年以上前の海に生息した節足動物の仲間、「モスラ・フェントニ」。その化石60点あまりを研究した論文が発表された。新たに名付けられたこの古生物は3つの目を持ち、ガが飛ぶような姿で泳いでいたことから「シー・モス(海のガ)」とも呼ばれる。
英国王立協会のオープンアクセス誌にこのほど発表された論文によると、モスラ・フェントニは節足動物の系統から初期に枝分かれした「ラディオドンタ類」に属する。
ラディオドンタ類はすでに絶滅しているが、その化石を調べることによって、昆虫やクモ、カニといった節足動物が進化してきた過程を解明することができる。研究を率いたカナダ・マニトバ博物館のジョー・モイシウク博士によると、節足動物は種類が多く、現生の全動物の中で8割以上を占めるとされている。
モスラ・フェントニの化石は保存状態が良く、ほかのラディオドンタ類にはみられなかった特徴として、16の節に分かれた腹部の後方にえらがあることが分かった。モイシウク氏によると、腹部に呼吸器官を持つ現生動物としては、ラディオドンタ類の遠縁にあたるカブトガニやワラジムシが挙げられる。
モスラ・フェントニのえらは、生息環境の中で酸素をできるだけ多く取り込むために使われたとみられる。別系統の生物が進化の結果、似たような構造を持つようになる「収斂(しゅうれん)進化」の一例ではないかと、モイシウク氏は指摘する。
研究チームに参加したカナダ・ロイヤルオンタリオ博物館のジャンベルナール・カロン博士は「初期の節足動物が驚くほど多様だったこと、遠い関係にある現生動物に匹敵するような順応を遂げていたことが分かる」と述べた。
ユニークな「海のガ」
モイシウク氏によると、モスラ・フェントニの姿は現生のどんな生物とも違う。爪は昆虫や甲殻類と似ているが、多くの節足動物が2個、あるいは4個の複眼を持つのに対し、モスラ・フェントニは頭の真ん中に大きな3番目の目がある。
同氏はまた、「関係が近いわけではないが、モスラはエイに似た泳ぎ方をしていたようだ」と説明。「何対もあるひれを上下に羽ばたかせ、水中を飛ぶように泳いでいた」「口は鉛筆削りのような形で、中がギザギザした面で覆われていた」との見方を示した。同様の特徴を持つ現生生物は見当たらないという。
モスラ・フェントニの大きさは大人の人差し指ほどで、泳ぐためのひれがどことなくガに似ていることから「海のガ」というあだ名がついた。
爪に生えているとげは1本1本が長く、表面はなめらかで先が枝分かれしている。モイシウク氏によると、「これでどうやって獲物を捕らえたのかはよく分からないが、とげの先でつかんで口へ運んでいたのではないか」と考えられる。
モスラ・フェントニが何を食べていたのかを直接知る手がかりはないものの、同時期に生息していたギボシムシやゴカイなどがラディオドンタ類のえさになっていた可能性がある。そしてモスラ・フェントニ自体は大型のラディオドンタ類、たとえばエビのようなアノマロカリス・カナデンシス、巨大なクラゲのバージェソメデューサ・ファスミフォルミスなどのえさになったとみられる。