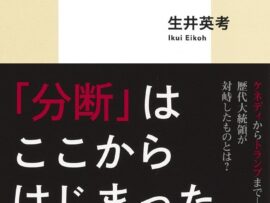大井真理子、ビジネス記者
今月18日に江藤拓農林水産相(当時)が、米は支援者が「たくさん」くれるので買ったことはない、と発言したとき、彼が狙ったのは笑いを取ることだった。
ところが、代わりに怒りを買うことになり、辞任に追い込まれた。
日本では数十年ぶりとなる生活費の危機的な上昇が続いており、影響は主食の米にも及んでいる。米の価格はここ1年間で2倍以上に上昇。輸入米はわずかしか出回っていない。
江藤氏の発言があったのは、自民党佐賀県連が佐賀市で開いた政治資金パーティーでの講演だった。江藤氏はその後、「言い過ぎた」として謝罪。野党側が不信任決議案を提出する構えを見せると、農相を辞任した。
江藤氏の事実上の更迭は、支持率低下に苦しんでいる石破茂首相の少数与党政権にとって、新たな打撃となった。
日本では米が大きな社会問題の原因となることがあり、米不足で政変が起きたこともある。1918年に起きた「米騒動」では、当時の政府が倒されている。
そのため、米の価格の高止まりが石破氏の支持率急落に一因になっているのは、それほど驚くことではない。
「政治家の方ってスーパー行かないですよね」と言うのは、横浜で暮らす樋口メモリさん(31)。
「この前、スーパーのお米の棚に二つしか置いてなくて、それが1袋5キロで4000円くらいしてるんですよ。その前で女性の方がしゃがみ込んで、ずっと悩んでたんですよ。それを見て、こんな姿、政治家に伝わらないよなと思って」と怒りをあらわにする。
生後7カ月の長女を育てる樋口さんは、産後の回復のためにも、今後作る離乳食にも、米が必要だ。
「幼児食になったら、モリモリ食べてほしいなと思っているので、あまりにお米が手に入らなくなったら、たぶん親の分を減らして、子供にあげたいなとは思っています」
■なぜ急騰しているのか
米価格の高騰は、数十年ぶりのインフレに苦しんでいる家計やビジネスに打撃を与えている。
おかわり無料のご飯を提供してきた多くの飲食店は、それをやめざるを得なくなっている。
では、なぜ米の値段は急に上がったのか?
シンプルな需要と供給の問題だと説明するのは、茨城大学の西川邦夫教授。ただ、その原因は政府にあると言う。
「2023年から2024年にかけて、政府の需要見通し680万トンに対して、実際の需要量は705万トンに上振れしました。インバウンドやコロナ禍明けの外食需要増加、コメの値ごろ感などのためです」
「一方で、生産量は661万トンに過ぎませんでした。農業者は過剰生産を防ぎ、米価を維持するために、政府の需要見通しにもとづいて生産を抑制してきたので、需要量に対して生産量が少なくなりました」
日本政府は1995年に食糧管理制度を廃止している。だがその後もJAを通じ、米の生産を調整している。
農水省の広報担当は、米の需要の急増は確かにあったとBBCに説明。原因として、他の食料品に比べて米は値段が比較的手ごろだったことや、外国からの訪問者が増えたことなど、いくつかの点が挙げられるとした。また、気温が異常に高かったため米の品質があまり良くなく、それも生産量の減少につながったとした。
新潟で代々、家族と米農家を営む笠原広祐さん(59)は、1俵(約60キログラム)の米を作るのに「人件費から、機械の償却、肥料など何から何まで入れて1万8500円くらいかかる」と言う。
一方、2024年の新潟での米の買い取り価格は1俵1万9000円。40年前と同じ値段だ。つまり米農家はもう何年も、利益を得ることができていなかった。
「減反政策というのもあって、各県に今年はこれだけ減反しましょうよ、そうしないと余剰なコメが出てきますからというものを政府とJAが打ち合わせしながら決めてたんですね。それを守ってくれた自治体には減反奨励金を払って、公共事業に絡めて、減反してくれた場合には、農林水産省の予算を多めにつけるということも3、4年前まではやっていた」と言う。
農水省の広報担当は、米から麦や大豆などに転作した場合に、政府が補助金を出してきたことを認めている。
一方で若手の農家は、JAを通さず、米を必要とするところに直接売ることを選んできた。
「この5、6年は加工米とか飼料米とかの数字が増えてました」と言うのは、兵庫で農業を営む田渕真也さん。
米が余っていた時は、値切られる米を作るより、「ほしがって頂けるところ、飼料米とか酒蔵さんとかおかき屋さんとかに出した方が、不毛な闘いをしなくて済んだ」からだ。
しかし、長年値切られる側だった立場は逆転した。1俵の値段は今、4〜5万円に高騰している。
国民の怒りを鎮めるため、政府は3月に備蓄米の放出を開始した。
近年は震災などの時しか放出されておらず、異例の決断だった。
「そもそも備蓄米は値段の調整とかでは出さないという認識だったんです。なんでかっていうと、過去にそれやって大暴落を起こしたことがあったから」と田渕さんは話す。
「当初出さないという方針だったのに、世論で変わっちゃうことに怖さを感じました」
備蓄米を放出して2カ月がたっても、米の値段は下がらないどころか上がり続けている。この状況を受け、農林水産省は5月から7月まで毎月10万トンずつ追加で放出すると発表した。
消費者が苦しんでいる一方で、「今年はやっと、もうけられる年だなというのが、稲作農家の気持ちです」と田渕さんは言う。「この十年くらい、農家もお米屋さんもほぼ利益なしで、薄利で回してるというのが続いていました」。
米の値段の高騰は日本に限ったことではない。
世界の米生産量の3割を占める東南アジアでも、環境の変化などが原因の米不足が続いている。
日本の消費者は日本の米を好むと言われるが、値段の高騰を理由に、政府は25年ぶりに韓国の米の輸入を決めた。
石破茂首相は、アメリカとの関税交渉のカードとして、米国産の米の輸入を増やす可能性も示唆している。
では、樋口さんのような消費者は、外国産の米を買うのだろうか。
「躊躇(ちゅうちょ)しますね」と樋口さんは語った。
「地産地消と言われて久しいですけど、やっぱり国産のものを、農家さんもちゃんと稼げて、私たちも安心して食べられる環境を、政府には作り続けてほしいです」
今後の政策については、米農家の中でも意見が割れている。
価格が下落した時に農家の所得を確保するため、戸別の所得補償を支持する意見もあるが、「それはもうやめてほしいなというのが僕らの感想です」と田渕さんは話す。
「米農家が減って大変だと皆さん言うんですけど、数が減ったとしても吸収し切れるので、ある程度減っていただいた方が効率が上がります」
「それを下手に国の施作で、言い方悪いですけど、60代、70代のおじいちゃん、おばあちゃんがこちょこちょやってる。もうけも度外視して、農協が安い値段でかなわんなと言いながら作られる。そういうのが、僕らとしては非常につらい」
こうした見解に、笠原さんは反対だ。「こういう田舎に住んでいると農業というのはコミュニティーなんですよ。コミュニティーの源で、農業があるから、役務の労働をしたり、お互いに助け合いながら生きているんですね。それを大規模農家の意見だけ当てはめて、やめればいいじゃないと言い出すと、小さい田舎はなくなっていきますね。山は荒れ放題になる」
笠原さんは、米1俵の買い取り価格を3万2千円から3万6千円で政府が保証すれば、農業離れも止まるだろうと言う。
米は、江藤氏の辞任問題でも明らかなとおり、日本の政治家にとっても非常に気を使う問題だ。夏に参院選を控えており、農家と消費者、特に高齢者を喜ばせることが、票を得るうえで重要になっている。
(英語記事 How a joke about rice cost a Japan cabinet minister his job)
(c) BBC News