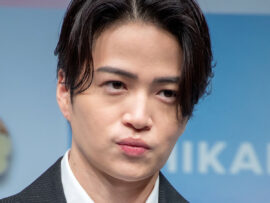かつて「アメリカの最も長い戦争」と呼ばれたヴェトナム戦争(米正規軍派兵から約8年間)は、現在ではアフガン戦争(約20年間)にその座を譲りました。しかし、その長さ以上に、ヴェトナム戦争がアメリカ社会に与えた深い傷と広範な影響は、現在に至るまで尾を引いています。新刊『アメリカのいちばん長い戦争』(集英社新書)は、この歴史的な転換点を追いながら、ヴェトナム戦争が残した記憶が現代のアメリカ社会にどのように刻まれているかを深く掘り下げています。著者である社会学者・人類学者でアメリカ研究者の生井英考(いくい えいこう)氏は、その専門知識と長年の研究経験に基づき、現代アメリカの混迷と分断の根源がヴェトナム戦争にあると説きます。
生井英考氏とヴェトナム戦争研究の軌跡
生井英考氏は1954年生まれの慶應義塾大学卒業のアメリカ研究者であり、2020年春まで立教大学社会学部教授、同アメリカ研究所所長を務めていました。彼のヴェトナム戦争への関心は、米留学中にヴェトナム帰還兵との交流を通じて深まりました。反戦世代より年下で、当時は戦争を身近に感じなかったという生井氏ですが、80年代の渡米を機に研究を本格化させ、1987年には最初の著作『ジャングル・クルーズにうってつけの日――ヴェトナム戦争の文化とイメージ』を上梓。この著作は、ヴェトナム戦争後のアメリカの社会・文化史と彼自身の経験を織り交ぜたもので、高い評価を得ました。
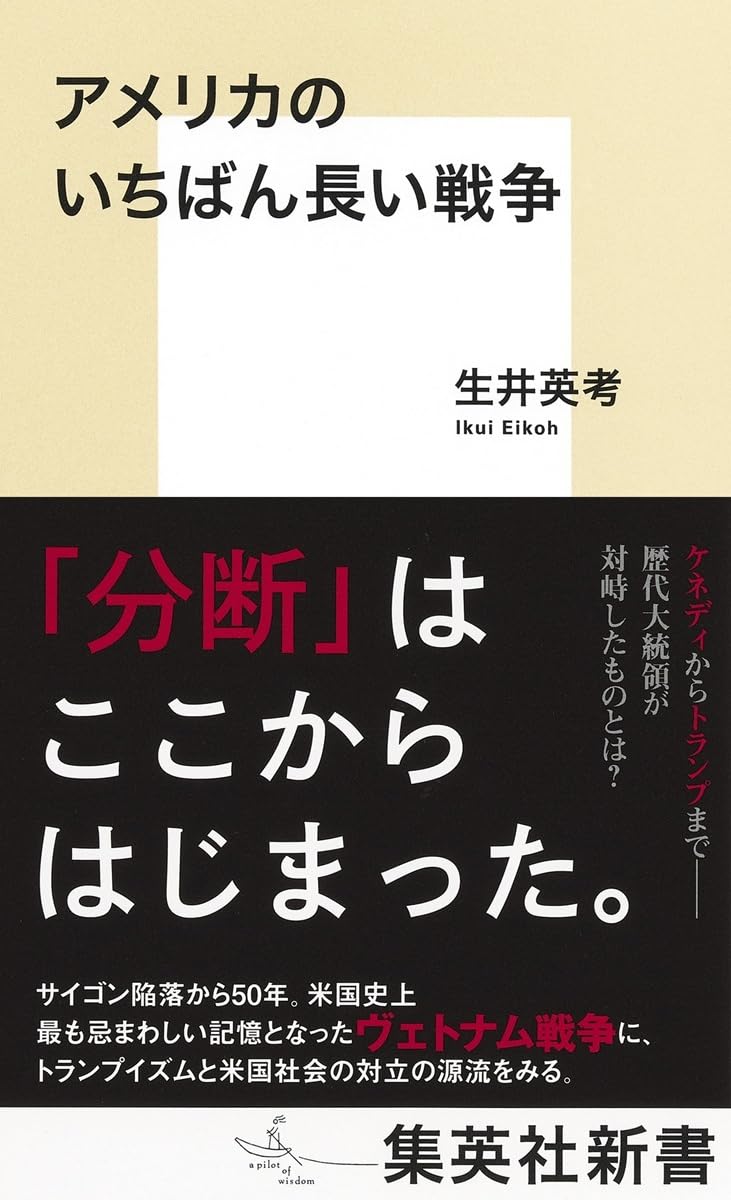 アメリカ研究者 生井英考氏の肖像。『アメリカのいちばん長い戦争』著者
アメリカ研究者 生井英考氏の肖像。『アメリカのいちばん長い戦争』著者
その後、1995年のアメリカとヴェトナムの国交正常化を受けて、関係性の変化を取り込んだ続編『負けた戦争の記憶 ―― 歴史のなかのヴェトナム戦争』を2000年に出版。今回の『アメリカのいちばん長い戦争』は、氏にとって3冊目のヴェトナム戦争関連書籍となります。長年にわたり、生井氏はヴェトナム戦争がアメリカにもたらした文化的・社会的な影響を多角的に分析し続けています。
9.11以降の対テロ戦争とヴェトナムの影
2001年の同時多発テロ(9.11)以降、アメリカはアフガニスタンやイラクでの「対テロ戦争」へと突入しました。これらの戦争もまた、ヴェトナム戦争と同様に、その正当性や目的の曖昧さが議論の的となり、多くの混乱を生み出しました。生井氏は、こうした現代の紛争が再びヴェトナム戦争を想起させると指摘します。「今のアメリカ社会の混迷や分断は、その根っこを辿って行くとヴェトナム戦争に行き着くんじゃないか、と」。この洞察が、彼に「もう一度初心に返るつもりで、この本を書いてみよう」という決意を促しました。
ヴェトナム戦争は、アメリカが南北に分裂したヴェトナムの南側政権を支援する形で軍事介入し、1965年以降、泥沼のジャングル戦に深く引き込まれた歴史があります。宣戦布告はなく、目的も大義も不明瞭なゲリラ戦が主体となり、敵味方の区別が困難であったため、参加した将兵たちの間で戦闘ストレスが激増しました。この戦争は、アメリカ史上初めて「負けた戦争」としても記憶されています。その記憶と教訓は、その後のアメリカの外交政策や社会心理に深く影響を与え続けています。
結び
生井英考氏の新著『アメリカのいちばん長い戦争』は、単なる歴史の振り返りにとどまらず、ヴェトナム戦争の遺産が現代アメリカ社会の混迷といかに深く結びついているかを明らかにします。アフガン戦争という新たな「最も長い戦争」を経験したアメリカが、今一度ヴェトナム戦争の記憶と向き合うことの重要性を説く本書は、歴史を学ぶことの意義を改めて私たちに問いかけます。現代アメリカの政治的・社会的課題を理解する上で、ヴェトナム戦争が残した文化的、心理的な影響は不可欠な視点であり、本書はその深い洞察を提供してくれるでしょう。
参考資料
- 生井英考 著 (集英社新書) 『アメリカのいちばん長い戦争』.
- 生井英考 著 (筑摩書房) 『ジャングル・クルーズにうってつけの日――ヴェトナム戦争の文化とイメージ』.
- 生井英考 著 (岩波書店) 『負けた戦争の記憶 ―― 歴史のなかのヴェトナム戦争』.
- Yahoo!ニュース (記事掲載元): https://news.yahoo.co.jp/articles/e1606349da95a1e2e2355ea615781e0787c86bea