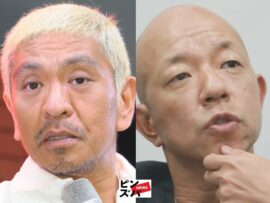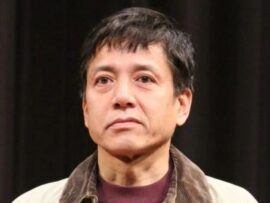登録児童数も待機児童数も増加傾向
共働き家庭などの小学生を放課後や長期休みに預かる「放課後児童クラブ」(以下、学童保育)は、子どもにとって家庭や学校以外のサードプレイス(第3の居場所)として重要な存在だ。現在は登録児童数、待機児童数ともに増加傾向にあり、SNSでは「学童落ちた」という保護者の書き込みも多く見られる。待機児童の解消に向けた受け皿の整備が急がれるが、待遇面の改善が進まずに人材不足の状況が続くなど課題も多い。学童保育の現状や課題について取材した。
【グラフを見る】学童の登録児童数は全国で151万9952人、待機児童数は17,686 人(2024年5月1日時点)
一般的に言われる「学童保育」は、正式名称を「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)」という。これは、児童福祉法に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に、授業の終了後などに適切な遊びや生活の場を与えて健全な育成を図るための事業と位置づけられている。
登録児童数は右肩上がりで増えており、こども家庭庁の「令和6年 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況」によると全国で151万9952人、待機児童数は1万7686人に上る(2024年5月1日時点)。
「小1の壁」に加えて「小4の壁」も…
現在の登録状況について、工学院大学教授でこども環境学・教育学・子どもの権利論を専門とする安部芳絵氏は「2024年度の小学1年生は、全体の半数ほどにあたる約45万4000人が5月時点で学童保育に登録している。6年生までの全学年で見ると、小学生のおよそ4人に1人が登録しており、学童保育に登録する児童は人数も割合も増えている」と話す。
しかし、希望者全員が学童保育を利用できるとは限らず、待機児童が出ている自治体もある。一般的に、保育園から学童保育に切り替わる「小1の壁」、学童保育の対象年齢から外れることもある「小4の壁」に頭を悩ませる保護者は多いといわれている。
「『小1の壁』では、小学校入学のタイミングで学童に入れなかったり、朝・放課後・長期休みの子どものタイムスケジュールと保護者の勤務形態が合わなかったりして、仕事と子育ての両立が難しくなるケースが見られます。
自治体によっては学童保育の対象を小3までとしていたり、低学年の子どもを優先的に受け入れたいという意向が働いて自主的に退所を余儀なくされたりするのが『小4の壁』で、2024年5月時点の待機児童数は小学4年生が5707人と最も多く、全体の32.3%を占めています。学童保育を利用できなくなり、放課後の居場所を確保するために仕方なく通塾を始めるケースも少なくありません」
東京に住むライター・コラムニストのせきねみきさんは、今年この「小4の壁」にまさに直面することとなった1人だ。
「4月に4年生になる長男が学童に入れませんでした。学童は1年生のときから通っていて、実は3年生のときも入れなかったのですが、待機が少なく昨年は5月から利用できました。今年は待機児童が私の前に30人以上もいるそうで、繰り上がりでの利用は期待できないと思います」
せきねさんが住む地域では、1〜2年生の希望者は大体学童に入れるという。たしかに4年生で学童に通う子は少ないというが、当初は学童が利用できない生活に不安を抱えていた。ただ、子どもが友だちと遊ぶ約束をしてくることも増え、現状で困ったことは起きていないという。
「当面の悩みは、夏休みなどの長期休暇の過ごし方をどうするかです。これまでは毎日学童に行っていたので、まだ何も考えていません。塾には通っておらず、サマーキャンプなどに行かせるのも一時的な対応になってしまうため、ひとまず児童館に遊びに行ってもらうのがいいのかなと思ってはいるのですが……」
夏休みとなると、放課後だけでなく丸1日を過ごす居場所について考えなくてはならない。せきねさんの住む地域にある児童館では、併設の学童エリアには入れないものの、事前申請をすればお弁当を食べて1日過ごすことも可能だというが、まだ頭を悩ませているようだ。
「フリーランスとして働いており、開業届に記載されていた住所の兼ね合いで在宅扱いと判断されたようです。取材で外に出ることも多いですし、今後は下の子が学童を利用することも考えると、自治体には家庭の実態にあった対応、支援をしてほしいと願っています」