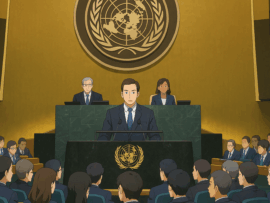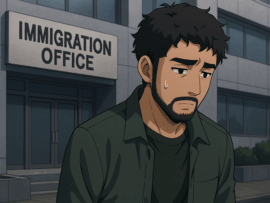[ad_1]
古今東西の小説家、詩人、芸術家、音楽家、政治家、思想家たちは、どれほどの愛をもってペットに接し、そして別れに向き合ったか。『ペットを愛した人たちがペットロスについて語ったこと 作家・アーティストたちの152の言葉』(フィルムアート社、2025年5月24日発売)には、心温まるエピソードが満載されている。その中から、ヘレン・ケラー(1880-1968)を支えた愛犬に関するエッセイを紹介する。
■犬たちの屈託のない明るさ
幼いころから、ヘレン・ケラーの世界は動物たちに支えられていた。
1882年、生後1歳半のときにかかった原因不明の病でケラーは視力と聴力を失った。けれども、8歳になるころには、すでに家族の飼い犬に守られていると感じていた。親戚へ宛てたこんな手紙がある。「ジャンボはとてもたくましく、忠実な犬です。夜もわたしたち家族を守ってくれます」。
彼女の教育に尽くした、パーキンス盲学校卒業の家庭教師アン・サリヴァン・メイシーの功績は広く知られているが、犬たちもまたかけがえのない役割を果たしていた。
「わたしが多くの犬たちとすてきな関係を築けたのは、その屈託のない明るさのおかげです」と、ケラーはのちに振り返っている。「たいていの犬は、わたしが目も耳も不自由であることにすぐに気づきます。わたしが近づくと、つまずかないように気づかって立ちあがるのです」。
マサチューセッツ州ケンブリッジにあるラドクリフ・カレッジに入学したころには、ケラーの偉業は広く認められていた。在学中に自伝『わたしの生涯』を発表した彼女は、世界的な活動家、教育者、社会改革者としての道を歩みはじめる。
キャンパスでは、“フィズ” の愛称で呼ばれた献身的なボストンテリアのサー・トーマスが教室まで寄り添い、足もとで静かに横たわっていた。これは、盲導犬の訓練が正式におこなわれる以前の話だ。
とはいえ、フィズはつねにおとなしくしていたわけではなかった。ケラーは愛おしそうに語っている。「とても愛情深くて、駆け寄って飛びついてくるから、わたしを倒してしまいそうなこともあるのです」。
■3日間だけ視力を取りもどせたら何を見たいか
[ad_2]
Source link