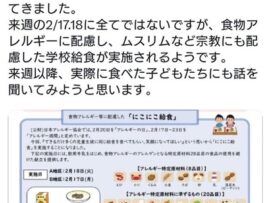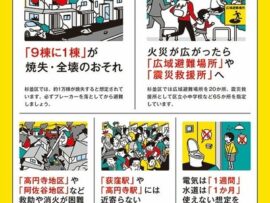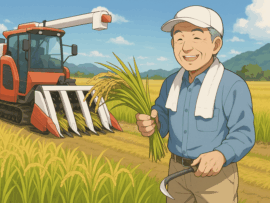[ad_1]
蔦重に500両で身請けさせたい
蔦重こと蔦屋重三郎(横浜流星)にとっては、かつて世話になり、手助けをし、また、眼の上のたんこぶでもあった地本問屋の鱗型屋孫兵衛(片岡愛之助)。だが、海賊版に手に染めて摘発されたダメージが大きく、再起できないまま店を畳むことになった。NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢〜』の第19回「鱗(うろこ)の置き土産」(5月18日放送)。
そこで蔦重が、吉原内の稲荷神社に「鱗の檀那の店も、うまくいきますように」と祈願して、両手を合わせていると、後ろから女性が蔦重に抱きつき、合わせた蔦重の手に自分の手を重ねて、「わっちらの恋も、うまくいきんすように」といった。大文字屋の売れっ子の花魁、誰袖(福原遥)である。
蔦重は嫌がってため息をつき、彼女を振り払って「お稲荷さんの境内でこんな」というが、誰袖はまったく気に留めず、「お稲荷さんはお怒りになりんせんよ。だってわっちら、夫婦(めおと)になりんしたゆえ」といって、1枚の証文を蔦重に見せた。そこには「誰袖は蔦屋重三郎に500両にて身請けを許すこととす」書かれ、大文字屋の楼主、市兵衛(伊藤淳史)の署名があった。
「親父様から遺言をいただきんした」と誰袖。大文字屋市兵衛は少し前に病死したが、いまわの際に、誰袖は証文を無理やり書かせていたのだ。「これであとは兄さんが500両、支度するだけでありんす」。そういって誰袖はお稲荷さんに手を合わせ、「500両、500両、500両」と祈願をはじめたが、蔦重は顔をしかめて立ち去ってしまった。
幼少のころに吉原に売られて
続いて蔦重はひとり歩きながら、「ああいうのが大奥で毒盛ったりすんだろうな」とつぶやいたから、蔦重は誰袖のことをよほど煙たがっているという設定のようだ。しかし、蔦重はともかくとして、誰袖と身請けは切っても切り離せない。
それについては後述するとして、誰袖は小芝風花が演じて評判になった瀬川と入れ替わるように『べらぼう』に現れたが、じつは、以前にも登場していた。そのときはまだ女郎見習の振袖新造で、名も誰袖ではなく「かをり」。子役なので福原遥ではなく、稲垣来泉が演じていた。
誰袖の出自などについては、ほとんどわかっていないが、子供のころに吉原に売られた可能性が高い。吉原では、貧しい親が妓楼(女郎屋)に借金した担保として売られた娘は、まず禿と呼ばれ、花魁のもとで雑用をこなしながら作法を学んだ。少し成長して13〜16歳になると振袖新造と呼ばれて女郎の見習いを務め、おおむね17歳から客をとった。
むろん女郎にもランクがあり、蔦重の同時代には上から順に「呼出」「昼三」「座敷持」「部屋持」……などに分かれていた。このうち花魁と呼ばれたのは呼出と昼三で、場合によっては座敷持も花魁にふくめた。とくに呼出と昼三は、妓楼の格子越しに並んで客をとる張見世はせず、引手茶屋に上がった客の指名を受けると、禿や振袖新造らを引き連れて仰々しく練り歩いて引手茶屋にやってきた。これが花魁道中である。
[ad_2]
Source link