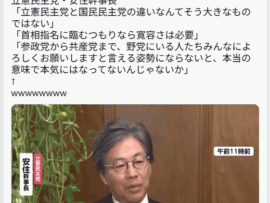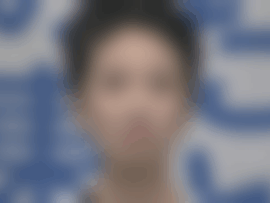[ad_1]
太平洋戦争末期の1945年5月25日深夜から26日未明にかけて行われた大空襲から80年となる。下町を焼き払った3月10日未明の東京大空襲に対し、山手地域に甚大な被害をもたらしたことから「山手大空襲」とも呼ばれる。B29による無差別爆撃は都心を火の海に変え、運行終了間近の地下鉄も巻き込まれることになった。関係者の証言を手がかりに「もうひとつの東京大空襲」を振り返る。(鉄道ジャーナリスト 枝久保達也)
● 東京大空襲の規模を はるかに上回る山手大空襲
米爆撃機B29を用いた東京空襲は1944年11月に始まった。当初の攻撃目標は武蔵野の航空機工場など軍需工場が中心だったが、1945年2月以降は市街地への無差別爆撃が始まった。3月10日の東京大空襲に続き、4月14日に北部、15日に南部、5月24日には南西部が焼き尽くされた。そして最後の仕上げとして、焼け残った都心及び西部(山手地域)を対象に行われたのが翌25日の空襲だった。
25日午後10時2分、陸軍東部軍管区司令部はB29の接近を知らせる「警戒警報」を発令した。上述の4月14日、15日の空襲のように、大規模空襲は日を置かずに続く傾向があったことから、前日に続く空襲を警戒していた人もいたようだ。
午後10時22分に「空襲警報」に切り替えられると、まもなくB29が東京上空に姿を現し、38分に先導機が第一弾を投下。午後11時過ぎから空襲が本格化した。この日、出撃したB29は474機、投下した焼夷(しょうい)弾は計3258トン。これは東京大空襲の325機、1665トンをはるかに上回る規模であった。
● 渋谷駅周辺は火の海 神宮前駅で足止めに
戦時中、戦局の悪化、空襲の激化とともに終車時刻は繰り上げられていき、ついに1945年に入ると午後10時30分頃まで早まっていた。東京大空襲(3月10日付記事参照)は深夜0時過ぎに始まったため、地下鉄は運行を終了していたが、午後10時過ぎに始まった山手大空襲では運行終了間近の地下鉄が巻き込まれることになった。
渋谷駅付近で地上に出る銀座線は当時、神宮前駅(現・表参道駅)の渋谷行ホームに空襲警報の発令を知らせるランプを設置し、発令時は運転を見合わせる対応を取っており、当日も終車近くの列車が神宮前駅で足止めとなった。
トンネルの先、渋谷駅周辺は火の海との情報が入ったため、車掌は神宮前駅から地上への脱出を試みたが、こちらも既に地上は猛火に包まれていた。
国鉄職員だった金山操(当時24歳)さんは『東京大空襲・戦災誌』で地上の様子を次のように書いている。
「人々の群れに押され、火に追い立てられて青山墓地から引き返して来た人びと。参道を渋谷橋の方から逃げ登って来た人達と、十字路付近で正面衝突して行き場を失い、渦を巻くようにして、地下鉄神宮前附近に集まって行く。渦は回るたびに厚く人の層を作って行く。誰もここが安全と思ってはいない。焼夷弾は爆弾も混じってるような爆発音を上げてるし、風速は30メートルに近く、猛り狂う火は、燃えるものは焼き尽くし、燃えないものは、天空に跳ねながら、じわじわと十字路付近を断末魔の様相に変えて行く」
神宮前駅からの脱出を断念した車掌は、渋谷駅に鉄道電話で問い合わせたが「乗客の扱いは、運転士とお前にまかせる」とだけ言って切れてしまった。車掌は戦時中に登用されたわずか19歳の女性だったが、運転士とともに数十人の乗客を線路に下ろし渋谷方面のトンネル坑口に向けて歩いていった。
[ad_2]
Source link