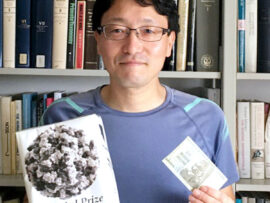映画や展覧会に行った際、期待していたほど楽しめなかった経験はありませんか?ベストセラー漫画の編集者として知られる佐渡島庸平氏は、「受け身の姿勢で作品を見ると、がっかりすることが増える」と指摘します。特に一見難しそうな西洋美術などを例に、芸術鑑賞を飛躍的に面白くする「超・能動的」な鑑賞方法を、著書『観察力を高める 一流のクリエイターは世界をどう見ているのか』から解説します。この方法は、単にアートを楽しむだけでなく、私たちの「観察力」を鍛え、世界をより深く理解するための強力なツールとなります。
受動的な鑑賞の落とし穴
美術作品を鑑賞する際、「あなたの見たまま、感じたままを言葉にすればいい」というアドバイスをよく耳にします。これは学校教育でも使われる常套句ですが、実際に感じたことを言葉にするのは容易ではありません。自分の心の中で何が起きているのかすら、よくわからない。だからこそ、「観察力」を鍛える必要があるのです。佐渡島氏は、絵を観ることを「絵を観て、動いた自分の心を観察し、その心の変化を生み出した絵のあり方と作者の意図に思いを巡らせる」行為だと定義しますが、これは多くの人にとってハードルが高いでしょう。例えばフェルメールの「牛乳を注ぐ女」を観て、すぐに「光の使い方に特徴があるな。ではどんな特徴か観察しよう」といった仮説を立てて観察できる人はほとんどいません。それは、「問い→仮説→観察」という観察サイクルを何十回も回した末にたどり着くレベルです。
なぜ「見たものを言葉にする」ことが重要なのか
では、どうすれば良いのでしょうか。その第一歩が、見たものを「ちゃんと言葉にする」ことです。佐渡島氏は、仮説とは頭の中のモヤモヤが言葉になったものだと言います。だからこそ、意識的に言葉にしようと試みる。仮説は言葉から始まり、そして言葉には力があると佐渡島氏は信じています。人間は全身で世界を感じ取りますが、言葉だけが意識的にコントロールできる道具です。言葉にすることで、情報を整理し、記憶し、頭の中で解像度を上げていくことができます。言葉は、人間が時空間を超えて携帯できる唯一の武器とも言えるのです。
言語化が「解像度」を高めるプロセス
見たものをひたすら言葉にする――。この行為を続けていると、自然と問いが浮かび上がり、そこから仮説が生まれてきます。観察には仮説が不可欠ですが、何も思い浮かばない時は、まず「言葉にすることだけ」を目的に観察を始めるのが有効です。そのプロセスが、対象の「解像度」を深めていくのです。具体的な例として、フェルメールが1657年頃に描いたとされる名画「牛乳を注ぐ女」を、愚直に言葉にしてみましょう。
 牛乳を注ぐ様子を捉えたイメージ写真。身近な動作も言葉にすることが観察の第一歩となる。
牛乳を注ぐ様子を捉えたイメージ写真。身近な動作も言葉にすることが観察の第一歩となる。
まず、目に入り、印象に残る順に言葉にしていきます。細部にも注目します。「絵の中央にメイドの女性が立っています。台座のようなテーブルの上には、ずんぐりとした陶器が置かれており、女性は両腕を使ってその中に牛乳をゆっくりと注ぎ入れています。テーブルにはエメラルドグリーンのテーブルクロスがかかっていて、様々な種類のパンが並んでいます。ちぎれたような小さなパンもあれば、バスケットに入った大きなパンもあります。また、銀製のポットのようなものも見えます。牛乳を注ぐ女性は白い頭巾を被り、髪は頭巾の中にきちんと収められています。上半身は肘までまくり上げた黄色い厚手の作業着を着ており、下半身は赤茶色のスカートで、腰には青いエプロンを巻いています。」
[internal_links]
観察力を高める言葉の力
このように、対象を「言葉にする」プロセスは、表面的な「感じたこと」を超え、具体的な細部を捉え、観察の解像度を高める有効な手段です。佐渡島氏が示すこの能動的なアプローチは、芸術鑑賞を深めるだけでなく、世界をより鋭く、深く理解するための基礎となるでしょう。
参考文献
佐渡島庸平『観察力を高める 一流のクリエイターは世界をどう見ているのか』(ダイヤモンド社)
元記事:ダイヤモンド・オンライン