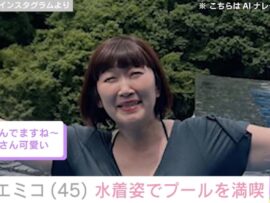5月30日、国家公務員総合職(いわゆるキャリア官僚)の春採用試験の合格者が発表された。合格者数は1793人と前年の1953人から1割弱減少したが、それ以上に注目すべきは出願者数の大幅な減少だ。前年の約1.36万人から約1.20万人へと1割以上減少し、結果として採用倍率は6.7倍と過去最低を更新した。これは、長年にわたり指摘されてきた就職先としてのキャリア官僚の人気低迷傾向が、今年も継続していることを明確に示すデータと言える。
 国家公務員総合職の新規採用者を迎える初任研修開講式、人材確保の重要性を示唆
国家公務員総合職の新規採用者を迎える初任研修開講式、人材確保の重要性を示唆
倍率低下が示す国家公務員総合職への関心低下
国家公務員総合職試験の採用倍率が過去最低を記録したことは、この職種への関心がかつてないほど低下している現状を浮き彫りにしている。出願者数の減少率が合格者数の減少率を上回ったことが、この倍率低下の直接的な要因だ。このトレンドは、特定の年に限ったものではなく、就職市場における国家公務員総合職の相対的な魅力が低下し続けているという構造的な問題を示唆している。特に優秀な人材の確保という点で、公的セクターは厳しい競争環境に置かれている。
東大生の「官僚離れ」と新たなキャリアパス
最終合格者のうち、東京大学出身者の人数も減少トレンドが続いている。今年の東大出身合格者数は171人であり、これは約10年前には400人を超えていたことを考えると、顕著な減少と言える。かつて「東大閥」として圧倒的な勢力を誇った時代は終わり、現在は最大勢力ではあるものの、その存在感は相対的に低下している。筆者自身も東大出身者として、自身の在学時(2006~10年)と比較しても、キャリア官僚が「就活勝ち組」のイメージから「数ある選択肢の一つ」へとランクダウンしている状況を肌で感じている。
代わりに東大生の間で人気が高まっているのは、外資系を中心としたコンサルティングファームやスタートアップ企業であるという。伝統的な大企業(銀行、商社など)がかつてのような受け皿ではなくなっている点は興味深い。これは、安定性よりも成長機会や多様な働き方を求める若者の志向の変化を反映している可能性が高い。
人材流出リスクとその行政機能への影響
キャリア官僚の人気低迷、特に東大生のようなトップ層からの人気低下は、「古くて新しい問題」として長年議論されてきた。かつてのように公的セクターに優秀な人材が過度に集中することも問題だが、その逆に、公的セクターから優秀な人材が払底してしまうこともまた深刻な問題を引き起こす。
例えば、現在人々の関心を集めている対米関税交渉のような国際交渉において、交渉責任者は大臣(政治家)であるが、その交渉に向けた情報収集や各種の案を作成するのは、紛れもなく官僚の仕事である。採用競争力の低下を背景に官僚の質が低下すれば、情報収集機能や立案機能が弱体化し、結果としてこうした重要な国際交渉において日本が不利になる可能性を否定できない。公的セクターにおける人材確保と育成は、国の機能維持にとって極めて重要な課題となっている。
まとめ
2024年の国家公務員総合職採用試験の結果は、キャリア官僚の長引く人気低迷と、特に最難関大学からの優秀な人材確保の困難さを改めて示した。採用倍率の過去最低更新や、東大出身合格者数の減少は、若手エリート層のキャリア選択が多様化し、公的セクターからコンサルやスタートアップといった民間セクターへと流動している現状を浮き彫りにしている。この人材流出は、政府の情報収集や政策立案能力に影響を与え、国際交渉を含む国の行政機能に潜在的なリスクをもたらす可能性がある。公的セクターが優秀な人材を引きつけ、その能力を最大限に活用できるような魅力的な職場環境を整備することが、喫緊の課題となっている。