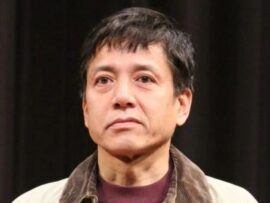政府備蓄米の市場放出により、一部で安価なコメの販売が始まったものの、国内のコメ価格の先行きは依然として不透明な状況が続いています。このような中、信用調査会社である東京商工リサーチや帝国データバンクから、コメ問題に関する新たなレポートが相次いで発表されています。これらの調査から見えてくる、日本のコメ業界の厳しい実態とはどのようなものでしょうか。
東京商工リサーチが5月4日に発表した調査によると、2024年のコメ農家(米作農業)の倒産と休廃業・解散の合計件数は89件に達し、統計を開始した2013年以降で最多を記録しました。この数字は、2022年の57件、2023年の83件からさらに増加しており、コメ農家の苦境が深まっていることを示しています。
 信用調査会社が発表した米に関するレポートデータを示すグラフイメージ
信用調査会社が発表した米に関するレポートデータを示すグラフイメージ
同社は、現在の状況を「コメ不足で生産農家が苦境に陥る異常事態」と指摘しています。不安定な価格変動に加え、生産コストの上昇が農家の経営を圧迫しています。さらに、後継者問題が深刻化している中で、これらの要因が倒産や休廃業を後押ししているとの懸念を示しています。コロナ禍での需要減退による価格下落傾向から一転、「コメ不足」報道が投機的な動きを呼び、需給バランスが崩れたことが、近年の価格高騰へと繋がっていますが、これが農家の収益安定には結びついていない現状が浮き彫りとなっています。
一方、帝国データバンクが4月6日に発表した調査では、2024年度(2024年4月~2025年3月)における米穀店の休廃業・解散が88件となり、コロナ禍以降で最多を更新したことが明らかになりました。コメ不足による仕入れ量の確保難に加え、大幅な価格高騰とそれを販売価格に転嫁できない状況が、米穀店の業績悪化に大きく影響しています。
経営者の高齢化も廃業の要因の一つとして挙げられており、帝国データバンクは2025年度も閉店や廃業、さらには倒産が増加する可能性が高いと予測しています。以前からコメ販売の自由化に伴う大手スーパーなどとの競争激化で苦境にあった米穀店は、近年の全国的なコメ不足により、そもそも仕入れ量が確保できないという新たな問題に直面しています。また、高騰する仕入価格を販売価格に十分に転嫁できないため、経営が悪化するケースが目立っています。一時的に在庫を高値で販売できた店も、その後の新米の仕入れコスト高騰により、収益力が大幅に低下しています。2024年度の米穀店の損益状況を見ると、約半数にあたる47.6%が業績悪化に直面しており、「売るコメがない」という状況が、米穀店の休廃業・解散にさらに拍車をかけていると言えます。
これらの信用調査会社による最新のレポートは、コメの供給不足と価格高騰が、生産者である農家だけでなく、販売を担う米穀店にも深刻な影響を及ぼし、双方で事業の継続が困難になるケースが増加している現実を示しています。異常気象や国際情勢、そして構造的な問題を背景としたコメを巡る厳しい環境は、今後も多くの事業者に影響を与え続ける可能性が高いでしょう。