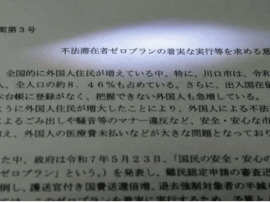中国山東省青島で6月25日から26日にかけ、上海協力機構(SCO)の国防相会議が開催された。中露が主導するこの枠組みを利用し、中国は米国によるイランの核施設攻撃を「国際法違反」と非難、イスラエルと共に批判対象と位置づけた。中国はSCOを通じて反米世論を拡大したい意向がうかがえる。
 中国・青島での上海協力機構国防相会議、董軍国防相とアジズ・ナシルザデ国防相が写真撮影に応じる様子
中国・青島での上海協力機構国防相会議、董軍国防相とアジズ・ナシルザデ国防相が写真撮影に応じる様子
会議の概要と中国の姿勢
会議を主宰した中国の董軍国防相は25日、加盟国であるイランのアジズ・ナシルザデ国防相と個別に会談を行った。中国はイランへの支持を明確に表明しており、ナシルザデ国防相からは「(中国の)理解と支持に感謝する。中国が地域の緊張緩和により大きな役割を果たすことを望む」との発言があった。
停戦合意への中国の反応
中国はかねてより仲介の意向を示していたが、結果として米国が仲介する形でイランとイスラエルの停戦合意が成立し、中国の存在感を示す機会は限定的となった。しかし、中国は原油輸入の4割以上をサウジアラビアやクウェートなど中東の産油国に依存しているため、停戦自体は歓迎する立場をとっている。一方で、対米で共闘関係にあるイランがこれ以上弱体化し、中国にとって不利な形で中東情勢が変化することも望んでいない。
 中国・青島で開催された上海協力機構(SCO)国防相会議の様子
中国・青島で開催された上海協力機構(SCO)国防相会議の様子
中国の対米けん制戦略
習近平政権は、SCO加盟国であるパキスタンや、加盟を目指す「対話パートナー」のエジプトなど、イスラム教国との関係を強化することで米国をけん制していく戦略であるとみられる。今回のSCO国防相会議も、その一環として利用されたものと考えられる。
まとめ
上海協力機構国防相会議は、中国が中東情勢における自身の立場を再確認し、特に米国主導の秩序に対抗するための手段としてSCOを活用する姿勢を示す場となった。イランへの支持表明やイスラム教国との関係強化を通じて、中国は地域における影響力拡大と対米戦略を進めている。
参考資料:
[Source link] (https://news.yahoo.co.jp/articles/6fdf362b11b4b49e7edfd719260e10872bc3791d)