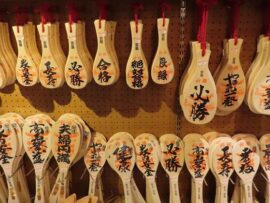7月20日投開票の参議院選挙が始まり、消費税の減税や給付が主要な争点の一つとなっています。石破茂首相は消費税減税について「お金持ちほど恩恵がある」と発言して注目を集め、また、ある野党は消費税を廃止すれば一世帯当たり年間30万円ほどの負担軽減になると主張しています。こうしたさまざまな主張が、実際の消費税負担の実態に即しているのか、政府統計を基にした推計から検証します。
公式統計にない「世帯別消費税負担額」
消費税が誰によって、どれだけ負担されているのか。所得税や住民税、社会保険料については、各世帯がどれだけ負担しているかを示す政府の統計が存在します。しかし、消費税については、政府が公式な統計として各世帯の負担額を示していません。
これは、家計の消費に関する政府統計が、消費税込みの消費額を集計しているためです。調査対象となる家計にとっても、税抜き消費額と消費税額を分けて正確に把握することは非常に難しいのが実情です。実際に、ご自身が年間にいくら消費税を負担したか、すぐに正確な金額を答えられる国民は少ないでしょう。
研究者による負担額の推計方法
そのため、各世帯の消費税負担額を把握するには、消費税法の詳細な知識を正確に理解した上で、研究者が独自に推計する以外に方法がありません。
[
買い物客が行き交う街の風景。消費税の負担は各々の生活に影響する](https://news.yahoo.co.jp/articles/f106cb126226096632c47c4ae8f4db8b7f97586a/images/000)
筆者(研究者)は、政府の家計消費に関する統計データを用い、標準税率、軽減税率の対象品目、さらに非課税品目を慎重に区分けしました。そして、これらの区分に応じた税込み消費額から、各世帯の消費税負担額を逆算して推計を行いました。
所得階級別の年間消費税負担額
推計結果を分かりやすく示すため、世帯の所得を低い方から高い方へと並べ、20%ずつの5つの階級(第Ⅰ階級から第Ⅴ階級)に区分し、それぞれの階級における世帯当たりの平均年間消費税負担額を算出しました。
その結果、所得が最も低い第Ⅰ階級の世帯における消費税の年間負担額は、約15万円という推計になりました。一方、所得が最も高い第Ⅴ階級の世帯では、年間の消費税負担額は約34万円と推計されています。
このデータから、消費税の負担額は、金額で見れば所得が高くなるにつれて増加することが分かります。これは過去の研究でも示されていたことですが、近年でも同様の傾向にあることが確認されました。石破首相が指摘する「お金持ちほど(減税の)恩恵がある」という点は、負担金額の面から見ればその通りであると言えます。
「廃止で30万円軽減」は高所得者層のみに該当
一方で、「消費税を廃止すれば一世帯当たり30万円の負担軽減になる」という野党の主張については、推計結果を見ると、これが当てはまるのは最も所得の高い第Ⅴ階級の世帯に限られることが分かります。低中所得者層の世帯では、消費税負担額が30万円に満たないか、第Ⅰ階級のようにその約半分の金額にとどまっています。したがって、消費税が廃止された場合の恩恵も、所得水準によって大きく異なるのが現実です。
まとめ
政府の公式統計では直接把握できない消費税の世帯別負担額ですが、研究者による詳細な推計からは、所得が高い世帯ほど消費税の負担額(金額ベース)が大きいことが改めて示されました。選挙で争点となる消費税に関する各政党の主張は、こうした所得階級による負担実態の違いを考慮して判断する必要があります。「お金持ちほど恩恵がある」という指摘は負担額の観点から正当性がありますが、「一律30万円軽減」という主張は、全ての世帯に当てはまるものではなく、特に低中所得者層にとっては実態と異なることが明らかになりました。選挙における消費税議論は、具体的なデータに基づいて冷静に判断することが重要です。