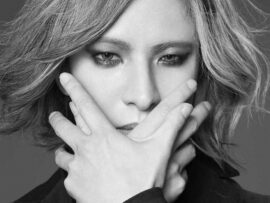日本の人気バスケットボール漫画の舞台としても知られ、巨大な鎌倉大仏が鎮座する神奈川県鎌倉市の寺院から、およそ一世紀にわたり異郷にあった朝鮮時代の伝統建築物一棟が韓国へ帰還しました。韓国の国家遺産庁と国外所在文化遺産財団は6月24日、ソウル市内の国立古宮博物館で説明会を開催し、朝鮮王室の祠堂建築物と推定される「観月堂(クァンウォルダン)」の建物の部材が、日本から搬出され約100年ぶりに韓国に戻ってきたと発表しました。今回の観月堂の返還は、所有者であった高徳院(鎌倉市)の佐藤孝雄住職(慶応大学教授、考古学)の決断により実現したものです。
観月堂、日本からの帰還へ:歴史的背景と経緯
国家遺産庁のチェ・ウンチョン庁長と国外所在文化遺産財団のキム・ジョンヒ理事長は、これに先立つ23日午後、観月堂を所有していた高徳院の佐藤住職と寄贈に関する協約を締結し、最近韓国に搬入された観月堂の部材を正式に譲り受けたことを明らかにしました。高徳院側は、2023年に境内にあった観月堂を解体した後、94件4900点あまりに及ぶ部材を韓国に搬出し、現在は京畿道坡州(パジュ)にある伝統建築修理技術振興財団の収蔵庫に保管されています。
 鎌倉の高徳院、鎌倉大仏の後方にあった観月堂の解体前の写真。朝鮮時代建築
鎌倉の高徳院、鎌倉大仏の後方にあった観月堂の解体前の写真。朝鮮時代建築
観月堂は、正面3間、側面2間の切妻屋根を持つ単層木造建築です。元々はソウル地域にあったと伝えられており、1924年に朝鮮王室が担保として提供し、朝鮮殖産銀行の所有となりました。その後、山一證券の初代社長である杉野喜精氏(1870~1939)に贈与されたものと推定されています。杉野氏は建物を解体して東京目黒の自宅に移築し、1930年代に鎌倉の高徳院に寄贈しました。観月堂は高徳院境内の鎌倉大仏の後方に再移築され、約90年間にわたり観音菩薩像を安置する祈りの場として使用されていました。この建築物が日本へ渡った経緯には、日帝強占期の歴史的背景が深く関わっています。
 観月堂の部材寄贈協約書に署名する高徳院の佐藤孝雄住職、国家遺産庁長、国外所在文化遺産財団理事長。
観月堂の部材寄贈協約書に署名する高徳院の佐藤孝雄住職、国家遺産庁長、国外所在文化遺産財団理事長。
返還の実現:住職の決断と協力
観月堂の韓国への帰還は、所有者である佐藤住職が「建物を韓国で保存することが適切である」と判断したことから始まりました。佐藤住職は数年前から観月堂の返還意向を韓国側に伝えており、これを受けて2019年からは国家遺産庁と国外所在文化遺産財団が本格的に関与しました。韓国の専門家チームは、観月堂に関する研究・調査、伝統的な色彩文様である丹青(タンチョン)の記録化と保存処理、そして精密な実測調査といった事業を継続的に進めてきました。この多年にわたる協力と専門的な調査が、今回の文化財返還を可能にしました。
 鎌倉の高徳院境内で行われた観月堂の解体工事風景。文化財移築
鎌倉の高徳院境内で行われた観月堂の解体工事風景。文化財移築
観月堂の価値:専門家による分析結果
韓国の専門家による研究・調査の結果、観月堂は建築学的には比較的シンプルな木組み構造であるものの、派手で格式ある意匠を追求した18世紀後半から19世紀後半にかけての、朝鮮王室の大君(テグン:王の嫡出子)クラスの祠堂に匹敵する規模の建物である可能性が高いと評価されました。建物の最上部材である梁(はり)を支える柱に植物のツルが連続する「波運(パウン)」という意匠が刻まれていること、大規模な建物の屋根側面に設置される草葉(チョヨプ)部材が見られること、鶴(ハク)の文様が彫刻された屋根部材の装飾があることなど、宮廷や宮家建築に特有の意匠要素が確認されています。
瓦類からは、龍(リョン)やクモ、コウモリといった多様な文様が入った平瓦当(ピョンプルムセ:平瓦の端を飾る瓦)が多数見つかっています。特に龍の文様は、宮廷に関連する建築的な要素として挙げられます。丹青の文様や顔料成分の分析からは、18世紀後半から19世紀後半に再度彩色された痕跡が確認されました。各層に施された丹青は、雲の形や「卍(マン)」形の格調高い文様で装飾されており、建物の高い地位を示唆しています。文様と色彩からは、朝鮮宮廷の丹青の特徴も見受けられます。ただし、建設工程を記録した上梁文(サンニャンムン)などの記録資料は解体時には確認されず、本来の建物の名称や建設場所、祀られていた人物などは今後の学術研究で解明すべき課題として残されています。
 返還された観月堂の内部と外部を詳細に捉えた3Dスキャン図面画像。伝統建築解析
返還された観月堂の内部と外部を詳細に捉えた3Dスキャン図面画像。伝統建築解析
移築による変化:建物の改変点
今回の解体に伴う精密な実測調査を通じて、日本に移築された後に建物の様式や構造が一部変更されていた事実も明らかになりました。例えば、基壇(建物の土台)に使用されている石材は、近隣の神奈川県や東京北部の栃木県で採掘された安山岩(あんざんがん)や凝灰岩(ぎょうかいがん)でした。また、基壇内部は充填されず空洞になっていました。これは既存の朝鮮時代の建物には見られない様式であり、東京や鎌倉に移築された過程で変更されたと考えられています。さらに、移築時には建物の後部壁の外側に、砂利やモルタルなどを混ぜた混合物で火防壁(防火壁)が建てられ、屋根には追加の覆い屋根(ふきいやね)が載せられていました。正面に設けられた欄干や、日本の木材商の情報が記された板壁材など、他の改変の痕跡も発見されています。これらの変更点は、建物が異国の環境に適応させられた過程を示す貴重な情報源となります。
 韓国・京畿道坡州の収蔵庫に保管されている、日本から移送された観月堂の解体部材。文化遺産保存
韓国・京畿道坡州の収蔵庫に保管されている、日本から移送された観月堂の解体部材。文化遺産保存
佐藤住職の貢献と今後の展望
解体と運送にかかる費用を全額負担し、観月堂の韓国帰還を主導した佐藤住職は、説明会にも出席し、建物の保存と文化遺産交流の支援のために、約1億円の基金を国外所在文化遺産財団に寄付する意向も表明しました。佐藤住職は、「韓国の専門家との協力によって、この建物の歴史的価値をより明確に理解することができた。最適な保存のためには韓国へ返還することが最善であるという国家遺産庁の要請に共感し、今回の寄贈を決断した」と述べました。さらに、「観月堂が約100年にわたり高徳院にあった歴史的な意味も記憶しつつ、韓国の適切な場所で、その本来の価値が回復されることを強く望んでいる」と語りました。国家遺産庁側は今後、坡州の収蔵庫で観月堂の部材の修復作業を進めるとともに、本来の設置場所などを明らかにする学術研究や、建物の保存・活用に関する具体的な計画を模索していく方針です。今回の観月堂の帰還は、日韓間の文化遺産を巡る歴史的課題において、民間の協力と専門的な知見が重要な役割を果たす可能性を示す事例と言えます。