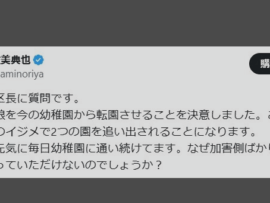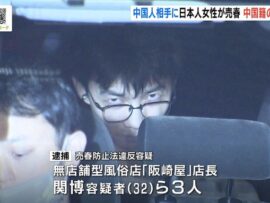中国は、東京電力福島第1原発の処理水海洋放出に伴い2023年8月から停止していた日本産水産物の輸入を、約2年ぶりに再開することを決定した。この動きは、日本との間の懸案事項解消に向けた中国側の譲歩と捉えられる可能性がある一方で、中国外務省は「海洋放出に反対する立場に変化はない」と強調しており、両国間の根本的な対立は解消されていない。特に、9月には抗日戦争勝利80年の節目を控えており、今後の対日姿勢が再び硬化する懸念もくすぶっている。
中国税関総署による輸入再開の発表と条件
中国税関総署は6月29日付の公告で、日本産水産物の輸入停止措置を同日付で解除し、輸入を再開すると正式に発表した。ただし、輸入再開にあたっては複数の条件が付されている。具体的には、日本政府機関が発行する衛生証明書、放射性物質の検査証明書、および産地証明書の提出が義務付けられる。実際の輸入が本格的に再開されるのは、日本側の水産業者の施設の登録手続きが完了し、中国側の基準を満たした後の見通しだ。
中国側の変わらぬ姿勢と今後の可能性
中国外務省の毛寧報道官は6月30日の記者会見で、今回の輸入再開決定について説明を行ったが、その中で処理水(中国は「核汚染水」と呼称)の海洋放出に対する中国の反対の立場は一切変わっていないことを改めて強調した。また、輸入された水産物について、検査などでリスクとなる要因が確認された場合には、「必要な輸入制限措置を直ちに講じる」可能性にも言及し、今後の展開によっては再び規制が強化されることも示唆した。なお、処理水放出以前から輸入が停止されていた福島県など10都県からの水産物については、今回の再開対象外であり、毛氏はこれらの地域の水産物について「食品安全の問題は科学の原則に基づき政策を決める」と述べるにとどめ、再開の見通しについては明確な言及を避けた。
国際社会の反応と歴史的背景
中国による処理水放出への強い批判は、国際社会において広く支持を得られず、ロシアや北朝鮮など一部の国にとどまったことも、中国の判断に影響したとの見方がある。また、近年、対米関係への対応に集中する必要があったことも、日本との間の特定の問題について矛を収める一因となった可能性がある。今回のタイミングでの輸入再開は、特に9月3日に予定されている抗日戦争勝利80年の記念日を前に、日本との間の目立った懸案を一時的にでも解消しておきたいという中国側の政治的な意図があった可能性も指摘されている。しかし、処理水問題に関する認識の溝は深く、今後、中国国内での対日感情の動向なども踏まえ、中国政府が再び強硬な姿勢に転じる可能性も否定できない状況にある。
結論
今回の中国による日本産水産物の輸入再開決定は、経済的な側面からは歓迎される動きだが、処理水問題を巡る両国の政治的な対立が根本的に解決されたわけではない。中国は引き続き強い懸念を示しており、今後の状況によっては再び関係が緊張する可能性も十分に考えられる。特に歴史的な節目を控える中で、中国の今後の対日姿勢は、日中関係の安定性を見通す上で引き続き注視が必要となる。