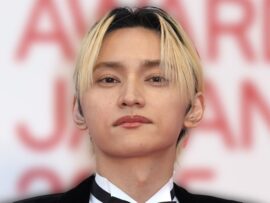元日産自動車COOで、現在は官民ファンドINCJ会長を務める志賀俊之氏は、日本の自動車産業が直面する深刻な危機、特に電気自動車(EV)への対応の遅れについて繰り返し警鐘を鳴らしている。EV市場が一時的に踊り場にある現状でも、氏が強い危機感を抱く背景には何があるのか。古巣である日産の経営不振にも自らの責任があるとする志賀氏に、その実相を聞いた。
 日本の自動車産業の危機について語る元日産COOの志賀俊之氏
日本の自動車産業の危機について語る元日産COOの志賀俊之氏
BYDの驚異的な成長と強さの源泉
BYDの2024年販売台数は427万台に達し、そのうち乗用車はEVが176万台、プラグインハイブリッド(PHV)が248万台と、わずか5年間で販売台数を9倍に伸ばす急成長を遂げている。特に注目すべきは、内燃機関を搭載するPHVを年間200万台以上販売する能力を有している点だ。BYDの強さの源泉はどこにあるのだろうか。
志賀氏は、BYD創業者の王伝福氏を高く評価している。1995年にバッテリーメーカーとして創業し、2003年に自動車事業へ参入。志賀氏自身、2005年頃にBYDが製造したエンジン車を試乗した経験があり、当時は他社から調達したエンジンや変速機を組み立てた、出来が良いとは言えないクルマだったという。しかし、王氏は当時から「いずれEVが普及するが、その前にエンジン車のハードウェアをしっかりと勉強しておかなければならない」と考えていた。内燃機関を製造していた時期は無駄ではなく、クルマづくりの基礎を学ぶための重要なステップだったのだ。
内燃機関技術へのBYDの取り組み
この春の上海モーターショーで、BYDが出展したPHVに水平対向エンジンが搭載されていたことは、自動車業界に驚きを与えた。これはエンジンルームを小さくして車両デザインをより洗練させるための工夫だ。日本の自動車メーカーがEV化やソフトウェア開発に注力するあまり、内燃機関を含むハードウェア開発への真摯な取り組みから目を背けている間に、BYDのようにソフトウェアとハードウェアの両面で力をつける企業が台頭している現実を、日本は直視する必要がある。日本の内燃機関技術が劣っているわけではないが、中国メーカー、特にBYDのPHVの技術レベルが著しく向上しているのは紛れもない事実だ。
自動車業界の変革と日本の課題
自動車産業の歴史を振り返ると、黎明期には多くの新興企業が生まれたものの、淘汰を経て現在の伝統的な自動車メーカーに集約されてきた。しかし、BYDのように設立から20年足らずで年間400万台規模の生産能力を持つ企業が登場したことは驚異的だ。これまで自動車産業は新規参入が難しく、参入障壁の高い業界であり、伝統的なメーカーはこの状況を享受してきた側面がある。
ところが、比較的モジュール部品の組み合わせで生産しやすいEVが登場したことで、この参入障壁が低くなった。一方、伝統的な自動車メーカーは、既存技術の改善を積み重ねる持続的イノベーションは得意とするが、ビジネスモデルそのものを変革する破壊的イノベーションには往々にして躊躇する傾向がある。これは過去の成功体験や積み重ねた知識が足かせとなり、次第に身動きが取れなくなるためだ。組織も縦割りに分断され、本来必要な新陳代謝も起こりにくい、極めてユニークな業界構造になっている。
現在の状況は、EVによってあらゆるものが一度「ご破算」となり、新しいメーカーが勃興している時代と言えるだろう。したがって、伝統的な自動車メーカーが生き残るためには、過去の成功体験を捨て去る「ゼロレガシー」という大胆なカルチャー変革を断行する必要があるのではないだろうか。