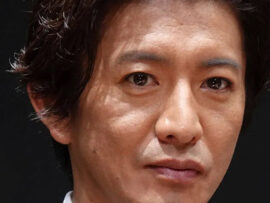最高裁判所は6月27日、国が2013年から2015年にかけて行った生活保護費の引き下げが、生活保護法に違反するとの判断を示しました。この判決に対し、多くの専門家は「不当な引き下げを強行した国の責任は極めて重い」として支持を表明していますが、世論の反応は必ずしも一様ではありません。「生活保護受給者は安易に多額の金銭を得ている」といった批判的な意見も少なくない状況です。その背景には、生活保護の支給額が年金受給額よりも多い場合があるという指摘も挙げられます。
生活保護制度に対する世論の反発の中には、事実に基づかない指摘も散見されます。例えばSNSプラットフォームXでは、「生活保護制度そのものは否定しないが、適切な社会復帰支援プログラムが必要」「何よりも自立が最優先されるべきであり、生活保護の支給には年限を設けるべきだ」といった意見が目立ちます。確かに、生活保護法の第1条には「最低限度の生活を保障する」とともに、「その自立を助長すること」が目的であると明記されています。しかし、専門家は、世論のみならず、法律の規定すら現在の社会状況に対応しきれていない現状を指摘します。
近年、生活保護は主に貧困に苦しむ高齢者のためのセーフティーネットとしての役割を強く担うようになっています。厚生労働省の調査データによると、生活保護受給世帯全体の55%を占める約90万7000世帯が65歳以上の高齢者世帯です。そのうち約84万5000世帯は一人暮らしの高齢者であり、特に女性の割合が多いことが専門家の調査で明らかになっています。さらに、75歳以上になると単身女性が占める割合は著しく増加し、2019年の調査では80歳以上の女性が全世代の中で最も高い生活保護受給率を示していることが確認されています。
データが示す受給者の「顔」:急増する高齢者世帯
厚生労働省のデータを見れば一目瞭然。受給者のうち「65歳以上」だけが急激に増加し続けている
厚生労働省データによる生活保護受給者(65歳以上)の推移グラフ
このような実態を踏まえると、80歳以上の高齢女性に対し、「社会復帰を可能にするプログラムを受講し、再び就労することで生活保護から脱却する」といったアプローチを働きかけるのは、現実的とは言えません。これは、生活保護の実情を正確に理解していない人々が、SNSなどで批判的な投稿を行っている現状を浮き彫りにしています。
高齢原告団と、年金だけでは「生きていけない」現実
今回の最高裁判決で勝訴を勝ち取った生活保護費引き下げ訴訟の原告団にも、高齢者の姿が多く見られます。時事通信が6月22日に配信した記事によると、全国の約1000人の原告のうち、裁判の長期化により高齢や病気が原因で232人がすでに他界しているとのことです。
生活保護受給者に高齢者が多い最大の理由は、公的年金の支給額の少なさにあります。特に女性の場合、長年にわたり専業主婦として子育てや介護に尽力し、子供が独立し、高齢の夫が先立った後に、あっという間に貧困状態に陥ってしまうケースが目立ちます。老齢基礎年金の平均月額は約5万7000円に過ぎず、この金額だけでは最低限度の生活を送ることが極めて困難な高齢者が多数存在します。一部の高齢者にとって、生活保護を受給しなければ文字通り「生きていけない」のが現実です。現役世代が病気や失業などで一時的に生活困窮に陥り、生活保護で立て直した後に自立を目指すという、かつての生活保護法の制度設計は、今日の高齢化社会の現実には完全には合致しなくなっていると言えるでしょう。
根拠なき批判と、無視できない年金との比較
生活保護制度の問題点を議論する上で、最も深刻かつ重要な論点は、このような高齢者の貧困問題なのです。しかし、XなどのSNSでは、「生活保護受給者には外国人が多い」「不正受給者には厳罰を科すべきだ」といった投稿が依然として目立ちます。これらの指摘が、実際のデータや実態に全く根差していないことは言うまでもありません。
一方で、「何十年も保険料を払い続けた国民年金よりも、生活保護の方が生活が安定する」という書き込みに関しては、決して事実に反しているわけではありません。これは、日本の年金制度、特に国民年金の支給水準の低さが背景にある、無視できない現実的な問題提起と言えます。
貧困の危機を示すイメージ写真
 貧困の危機を示すイメージ写真
貧困の危機を示すイメージ写真
今回の最高裁判決は、過去の不当な引き下げに司法の判断を下しましたが、生活保護制度が抱える根本的な課題、とりわけ高齢者の貧困という現実を社会全体が直視し、制度のあり方を再考する必要があることを改めて示唆しています。世論にみられる誤解を解き、データに基づいた冷静な議論を進めることが、今後の重要な課題となるでしょう。