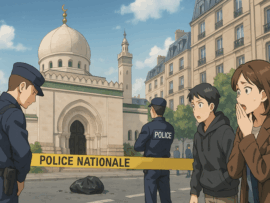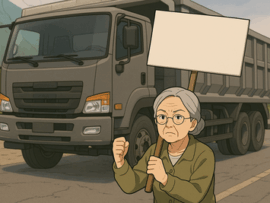英国の調査により、16歳から21歳の若者のほぼ半数が「インターネットのない世界の方がいい」と感じていることが明らかになりました。多くの若者がデジタル疲れを訴えており、特にソーシャルメディア(SNS)が自身の感情や精神状態に悪影響を及ぼしているという悩みを抱えています。これは、デジタル化が進む現代社会における若者のインターネットとの向き合い方に、大きな変化と課題が生じていることを示唆しています。
SNS利用と幸福感への影響、そして求められるルール
調査によれば、InstagramやTikTokなどのSNSを見た後に「幸福感が下がる」と答えた若者は70%に達しました。このデータは、承認欲求や他者との比較が生み出すプレッシャーが、若者の精神的well-beingを損なっている可能性を示唆しています。また、回答者の半数が「夜10時以降のアプリ使用を制限するルールがあった方がいい」と考えており、自制心だけではデジタル習慣を管理することの難しさを認識している様子がうかがえます。彼らは、ある程度の外部的な制限やガイドラインを求めていると言えるでしょう。
危険なオンライン行動の実態
さらに懸念されるのは、若者のオンラインにおける危険な行動が浮き彫りになった点です。調査対象者の約半数が「年齢を偽ってオンラインサービスに登録したことがある」と回答しました。また、同じく半数が「オンラインでの行動について親に嘘をついたことがある」と答えています。加えて、40%が偽アカウントを作成した経験を持ち、4人に1人以上が「他人になりすました経験がある」と認めています。これらの行為は、オンライン空間における匿名性や現実との乖離が悪用されやすい現状を示しており、青少年のオンライン安全保護が喫緊の課題であることを物語っています。
 スマートフォンを使用する若者、デジタル疲れやSNSの影響を示すイメージ
スマートフォンを使用する若者、デジタル疲れやSNSの影響を示すイメージ
時間制限だけでは不十分:広範な改革の必要性
専門家は、アプリの使用時間やスクリーンタイムに制限を設けるといった「時間制限」は一時的な対策にはなりえても、デジタルがもたらす有害な影響の根本的な解決にはならないと指摘します。NSPCC(子どもの保護を目的とする団体)のラニ・ゴヴェンダー氏は、より依存性を生みにくいプラットフォーム設計など、「広範な改革が必要」であると強調しています。有害なコンテンツのリスクは時間に関係なく存在するため、場当たり的な「時間制限」ではその脅威を完全に排除することはできません。プラットフォーム自体の構造的な問題に対処することが求められています。
パンデミックの影響と「安全設計」への提言
回答者の約4分の3が、パンデミック中にオンラインで過ごす時間が増加したと述べており、そのうち68%が「それが精神面に悪影響を与えた」と感じています。モリー・ローズ財団のアンディ・バローズ氏は、アルゴリズムが若者を有害な情報へと誘導する現状を憂慮しており、子どもをオンラインの危険から守るための「安全設計(safe by design)」を義務付ける法律の整備を急ぐべきだと強く訴えています。今回の調査結果は、次世代を担う若者たちが、デジタル社会の問題点をしっかりと認識し、現状を変えたいと強く願っていることを改めて示しています。社会全体で、彼らの安全と健全な成長のための環境整備に取り組む必要があります。
引用元:
Wonderful Engineering(Forbes JAPAN 編集部翻訳転載)