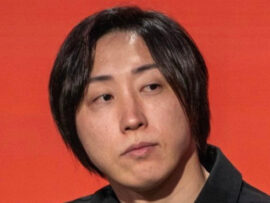セロトニンが心の安定に関わる脳内物質であることは広く知られています。実は、「噛む」という口の習慣を少し変えるだけで、このセロトニンを増やし、子供の思考力、精神状態、さらには姿勢まで改善する方法があると、現役ママ歯科医の生澤右子氏は語ります。生澤右子氏の著書『集中力が高まり、心の強い子になる!噛む力が子どもの脳を育てる』から、子供の脳の成長を促す口の習慣についてご紹介します。
セロトニンとは?脳のセロトニン神経の役割
セロトニンは、脳のセロトニン神経から分泌される神経伝達物質で、脳の広い範囲の神経活動を調整する重要な役割を担っています。セロトニンの重要性を世に広めた功労者として、東邦大学医学部名誉教授の有田秀穂先生が挙げられます。有田先生は「セロトニン欠乏脳」という言葉を用い、セロトニン神経の重要性とその活性化法、特に呼吸、歩行、そして咀嚼といったリズム運動の有効性を分かりやすく伝え続けてきました。口の習慣や歯医者とセロトニンに疑問を感じる方もいるかもしれませんが、セロトニン神経を活性化する鍵はまさにこれらのリズム運動なのです。
咀嚼が脳に与える科学的効果
著者は大学院で「噛むことによるセロトニン神経活性化」をテーマに研究を行いました。ガムを5分から20分噛むことでセロトニン神経が活性化し、鎮痛効果が得られるのではないかという仮説のもと、実験に励んだのです。「咀嚼というリズム運動が痛みを軽減する」ことを科学的に証明したこの論文は、幸いにも国際的に有名な『ペイン(PAIN)』誌に掲載されることとなりました。この研究は大きな反響を呼び、睡眠学の教科書に掲載されたり、海外からも問い合わせがあったりと、その重要性が認識されています。有田先生は、咀嚼は単なる消化機能だけでなく、脳に作用し、頭をスッキリさせ、気分を前向きにし、自律神経を整え、痛みを和らげ、さらには見た目も元気にすると、科学的に実証された研究成果を説明しています。
セロトニン神経活性化の具体的な効果
セロトニンの第一人者である有田先生が長年の研究で明らかにしたセロトニン神経の働きを日常生活に取り入れることで、現代社会で弱まりがちなセロトニン神経を元気に保つことができます。セロトニン神経が活性化すると、以下のようないい効果が期待できます。
- ストレスへの耐性がつき、感情の起伏が穏やかになる
- 姿勢が改善され、顔つきも引き締まる
- 集中力が高まる
- 覚醒度が上がり、頭が冴える
- 夜のスムーズな入眠を助ける
- 痛みに強くなる
このように、セロトニン神経の活性化は心身に多くの恩恵をもたらします。
日常でセロトニンを増やす方法
セロトニン神経を活発にする主な要素は、太陽の光を浴びることとリズム運動です。これらを日々の生活にうまく取り入れましょう。リズム運動は、始めてから約5分でセロトニン神経が活性化し始め、20分から30分でその効果がピークに達することが研究で分かっています。そして、その効果は約2時間持続します。このメカニズムを利用し、効果が薄れてきたら再度リズム運動でブーストすることを繰り返せば良いのです。咀嚼も効果的なリズム運動の一つであり、例えば朝食時に意識してよく噛む時間を設けることなどが挙げられます。
 子供たちが朝食をゆっくりと食べる様子。セロトニンを増やす咀嚼のリズム運動として効果的です。(画像はイメージ)
子供たちが朝食をゆっくりと食べる様子。セロトニンを増やす咀嚼のリズム運動として効果的です。(画像はイメージ)
さあ、今日から手軽にできる「セロトニン生活」を始めて、子供たちの健やかな成長をサポートしましょう。咀嚼のような日常的な習慣を見直すことが、彼らの可能性を大きく広げる第一歩となるはずです。
参考文献
- 生澤右子『集中力が高まり、心の強い子になる!噛む力が子どもの脳を育てる』(青春出版社)
- 『ペイン(PAIN)』誌掲載論文(咀嚼と鎮痛に関する研究)