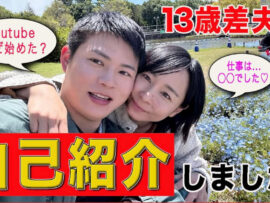年金制度改革関連法が6月13日に参議院本会議で可決・成立しました。この改正法の柱の一つに、基礎年金の水準を引き上げる措置(基礎年金底上げ策)が盛り込まれています。しかし、この底上げには将来的に年間2兆円程度の追加費用が見込まれ、国庫負担の財源確保が大きな課題です。厚生年金の積立金活用などの具体策は、世代間の利害が錯綜する問題を含んでいます。7月20日投開票の参議院議員選挙を前に、年金を含む社会保障改革の現状と課題を深く理解することが求められます。
基礎年金底上げの仕組みと財源課題
今回の年金制度改革における基礎年金の底上げ策は、財源が逼迫しがちな基礎年金を、比較的安定している厚生年金の積立金で支え、水準の維持・向上を図るものです。具体的な仕組みとして、厚生年金保険の加入者の報酬比例部分にかかるマクロ経済スライドの適用期間を2026年度以降も継続し、2036年度まで延長します。これにより、物価や賃金の伸び率よりも年金額の伸びを低く抑えることで生じる財源を基礎年金の方に振り替えます。さらに、厚生年金積立金の一部を基礎年金給付の財源として活用する財政措置も盛り込まれました。これは、基礎年金にかかるマクロ経済スライドの適用期間を短縮することを目的としています。
しかし、基礎年金の給付費用の半分は元々税金(国庫負担)で賄われています。そのため、基礎年金の水準そのものを引き上げると、当然その分だけ国庫負担が増加します。将来的に年間2兆円程度の追加費用が見込まれますが、その具体的な財源確保は示されていません。消費税が社会保障目的税であることから、消費税の増税での対応が事実上想定されています。この財源問題は、改革の最大の課題の一つです。
 基礎年金底上げ策が年金制度に与える影響を図解した表
基礎年金底上げ策が年金制度に与える影響を図解した表
世代への影響と公平性の定量評価
基礎年金底上げ策は、現役世代、将来世代、高齢世代の間で利害が錯綜し、世代間公平性が問われます。厚生年金のマクロ経済スライド延長は、現在の厚生年金受給者の年金額を実質減額させます。また、厚生年金積立金の活用は、将来世代への給付原資を減少させる側面を持ちます。さらに、国庫負担増による消費税増税などの可能性は、全世代、特に現役・将来世代の負担増につながりかねません。
こうした世代間の影響や公平性を定量的に把握するため、「世代会計」という分析手法が重要になります。これは、個人が生涯にわたり国へ支払う税金や保険料と受け取る年金などを現在価値に換算し、世代別に集計・分析する手法です。元の記事では、この世代会計を用いたシミュレーションを基に、世代間格差の問題を評価する視点を提供しています。
まとめと投票への示唆
基礎年金底上げを柱とする年金制度改革は成立しましたが、国庫負担増の財源確保や厚生年金積立金の活用を巡る世代間公平性の問題など、重要な課題を抱えたままです。特に現役・将来世代への負担増の可能性は避けられません。社会保障改革のあり方が問われる7月20日投開票の参議院議員選挙では、本改革が持つ課題と将来への影響を理解し、慎重な投票判断が求められます。
参照元
https://news.yahoo.co.jp/articles/178503245e599d34b085e061e21de202b99e236a