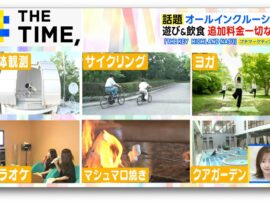参議院選挙が公示され、20日の投票日に向けて選挙戦が本格化しています。今回の最大の争点は「物価高対策」であり、与党と野党はそれぞれ異なる提案を掲げ、互いの政策を「バラマキ」と批判し合っています。しかし、国民全体にお金を分配するという点では、両者の提案に大きな違いはなく、その本質は「どちらもバラマキ」と言えるかもしれません。
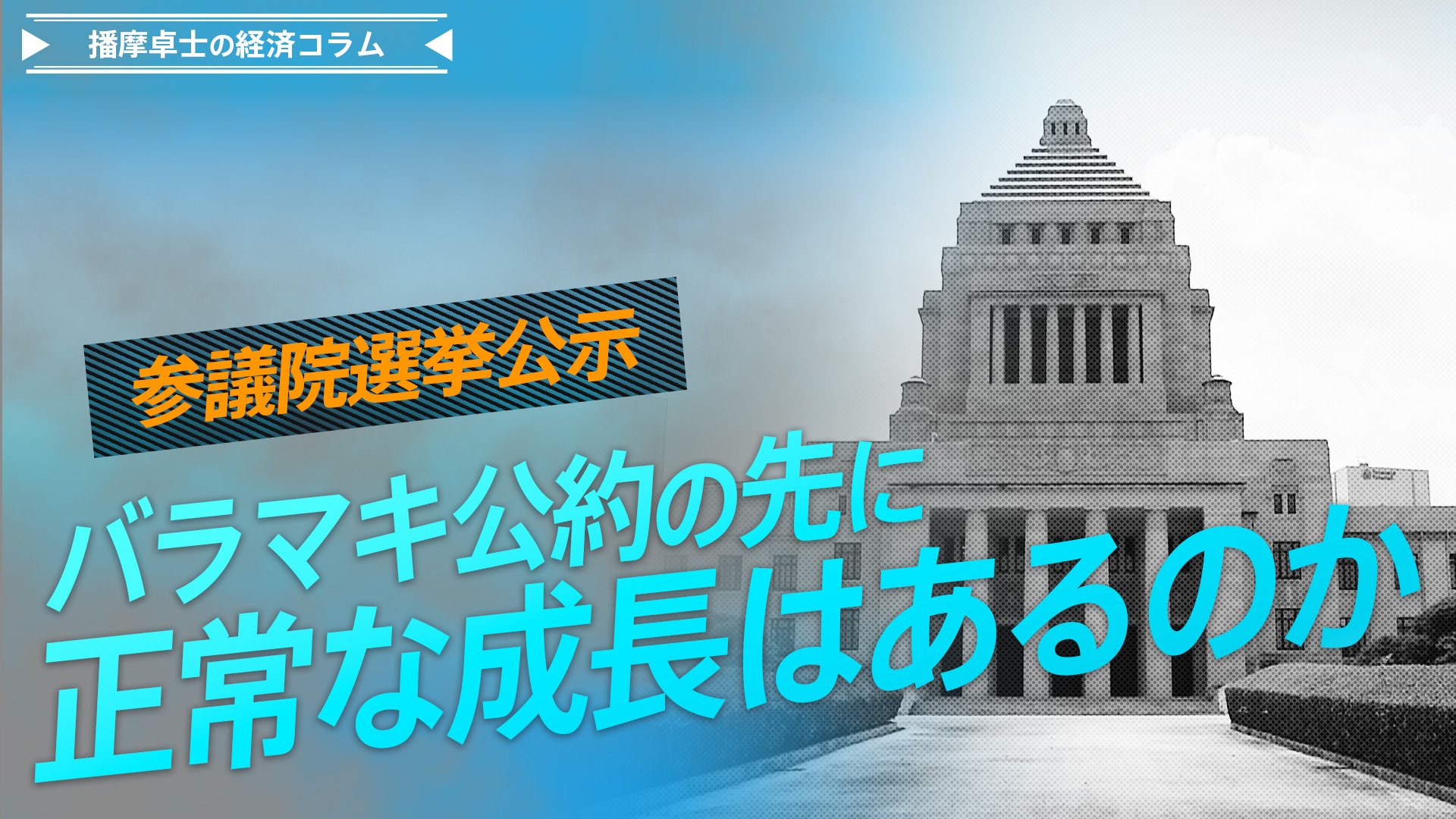 参議院選挙の論点となる物価高対策と給付金・減税論争
参議院選挙の論点となる物価高対策と給付金・減税論争
与党案も野党案も「バラマキ」なのか?
自民党と公明党が提示する案は、「国民全員に2万円」という給付金制度です。石破総理は、子供や住民税非課税世帯への加算がある点を挙げ、「メリハリがあり、バラマキではない」と説明しています。しかし、高所得者を含む国民全員に一律で2万円を配る以上、これをバラマキと呼ばないならば、他に何をバラマキと呼ぶのかという疑問が湧きます。
一方、野党側では、立憲民主党と日本維新の会が食料品に限定した時限的な消費税ゼロを、国民民主党は消費税全体の5%への引き下げを、共産党、れいわ新選組、参政党は消費税の廃止を主張しています。食料品であれ、一般物品であれ、消費をしない人はほぼいないため、これらの減税策も事実上、すべての人が対象となります。さらに、消費金額が多い、いわゆる「お金持ち」ほど減税による恩恵が大きくなる構造から見ても、これもまたバラマキの一種と言えるでしょう。消費税のあり方についての議論自体は重要ですが、短期的な景気刺激策や生活支援策としてではなく、より長期的な視点での税制全体の議論として行われるべき性質のものです。
本当に必要なのは「全員配布」か「対象限定」か
まず考えなければならないのは、現在の経済状況が、国民全員にお金を配らなければならないほど危機的な状況にあるのかという点です。大恐慌や新型コロナウイルスのパンデミック時のように、経済活動が広範囲に停止し、多くの人々が失業の危機に直面した際には、国民全体への現金給付などの政策は有効であり、国にしかできない役割を果たします。
しかし、現状はどうでしょうか。近年は2年連続で30年ぶりの高い水準での賃上げが実現し、多くの業種で人手不足が深刻化しています。マクロ経済的にも、需給ギャップはほぼ解消された状態にあります。このような状況が、過去の危機時と同様に国民全員への支援が必要なほど切迫しているとは考えにくいです。
現在の問題の本質は、物価の上昇率が予想以上に高く、その状態が長く続いている一方で、賃金などの収入が物価上昇に追いついていない人々が多数存在するという現実にあります。つまり、支援が本当に必要なのは、この物価高によって生活が困窮している人々です。生活に困らない高所得者層や、すでに賃上げによって物価高の影響を十分に吸収できている人々に対してまで、国が広くお金を配る必要はないはずです。
結論として、参議院選挙で提示される様々な物価高対策は、給付金であれ減税であれ、「バラマキ」という批判を受ける側面を持ち合わせています。重要なのは、こうした公約の表面的な部分だけでなく、その先にどのような経済効果をもたらし、真に支援が必要な人々へどのように手を差し伸べるのか、そして経済全体をどのように正常な成長軌道に乗せていくのか、その本質を深く見極めることです。
参考文献: Yahoo!ニュース/TBS NEWS DIG powered by JNN