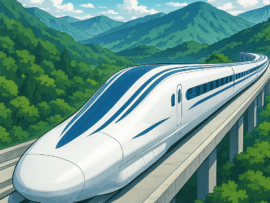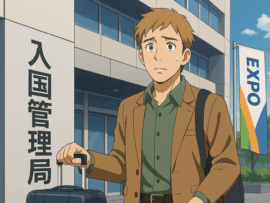大学受験は多くの若者にとって人生を左右する大きな転換点であり、どの大学に進学するかが、その先の就職活動に影響を与える日本の社会的な現実です。特に、地方の国公立大学と首都圏の難関私立、早稲田大学や慶應義塾大学(早慶)の間で、就職活動の結果に差が生じるという議論は、しばしば耳にします。教育専門家であり、著書『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が話題のびーやま氏は、この差は学力だけでない要因によると分析します。今回は、びーやま氏へのインタビューを通じて、地方国公立と早慶の就職活動における「本当の差」とその背景にある理由を深掘りします。
就職活動で早慶は地方国公立に「勝つ」のか?びーやま氏の見解
びーやま氏はまず、就職活動における早慶の強さは「本当に抜群」だと認めます。「これまで多くの学生にインタビューなどを行ってきましたが、早慶生の就活の強さは本当に抜群というか、『本当に私立?』みたいな印象です」と述べ、その影響力の大きさを語ります。特に大企業の新卒採用において、早慶の割合が非常に高いケースは珍しくなく、旧帝大や一橋大学、東京科学大学といったトップクラスの国公立大学以外では、大学名で早慶に劣後する場面があるのが現実だと語ります。
 大手企業の就職活動における内定や面接の場面をイメージさせる握手と書類
大手企業の就職活動における内定や面接の場面をイメージさせる握手と書類
学力だけではない?就活で差がつく「本当の理由」
国公立大学の学生は、受験科目が多く推薦入学が少ない傾向にあるため、基礎学力は高いのではないかという問いに対し、びーやま氏はそれを肯定します。「国公立大生のほうが受験時の科目数も多いですし、推薦なども少ないので、なにかと基礎の高さは感じます」と述べ、学力面では国公立大生が劣っているわけではないと強調します。
では、なぜ就職活動で差がつくのか? びーやま氏は、その主な理由を「地域と情報による差だけ」だと分析します。早慶は首都圏などの都市部にキャンパスが位置しているため、学生は様々な企業の説明会や面接に「フットワーク軽く行動」できます。また、企業には早慶のOB・OGが多く存在するため、就職に関する情報収集が非常にしやすい環境にあります。さらに「私立の中では1番」というブランドイメージも、就活を有利に進める要因になり得ると指摘します。一方、地方の国公立大学の場合、就職先として都市部の企業を希望する場合、就職活動のたびに長距離移動が必要となり、時間的、コスト的な負担が大きくなります。これは、学力や個人の能力とは関係のない部分で不利に働く要因となります。びーやま氏は、このように、大学で培った能力そのものよりも、大学の立地や集まる情報の差が、就職活動における有利不利に繋がっているのではないか、との見解を示しました。
びーやま氏の分析は、大学での学力や能力だけでなく、立地による情報アクセスやネットワークが、就職活動の成否に大きく影響している現状を浮き彫りにします。地方国公立大学の学生が持つポテンシャルを活かすためには、こうした学力以外の要因を理解し、戦略的に就職活動に臨むことの重要性が示唆されています。