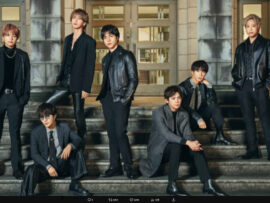現代のテレビドラマでは、従来のイメージとは異なる「未亡人」像が注目を集めています。夫との死別という経験を乗り越え、より強く、しなやかに、そして魅力的に生きる女性たちの姿は、視聴者に新たな価値観を提示しています。特にNHK連続テレビ小説『あんぱん』とフジテレビ系ドラマ『続・続・最後から二番目の恋』は、現代女性の自立と価値観の変化を映し出す象徴的な作品と言えるでしょう。
朝ドラ『あんぱん』が描く、前向きに生きる女性たち
現在放送中の朝ドラ『あんぱん』では、主人公・のぶの家族を中心に、夫を亡くした女性たちが多数登場します。主人公の若松のぶ(今田美桜)は、愛する夫・次郎(中島歩)を肺の病で失いました。戦時下という時代背景の中で、もし十分な治療が受けられていれば命を落とすことはなかったかもしれないという無念さが描かれつつも、のぶは長年のすれ違いを乗り越え、幼なじみの柳井嵩(北村匠海)と結ばれるなど、前向きに人生を歩み始めています。
のぶの妹・蘭子(河合優実)もまた、婚約者の原豪(細田佳央太)を戦死で失うという悲しい経験をしています。また、母・羽多子(江口のりこ)ものぶたちの父と病死で別れており、祖母・くら(浅田美代子)も最近、夫を亡くしています。これらの女性たちは、伴侶を失うという大きな悲しみを経験しながらも、決して立ち止まることなく、それぞれの方法で人生を切り拓いていく姿が描かれています。特に、戦後という困難な時代において、彼女たちのたくましく、そして健やかに生きる姿は、現代社会における女性のレジリエンス(回復力)と自己実現の可能性を強く示唆していると言えるでしょう。
 朝ドラ『あんぱん』より。夫を亡くしたのぶが幼なじみの嵩と結ばれる感動的な場面。現代ドラマが描く自立した女性、新しい未亡人像を象徴。
朝ドラ『あんぱん』より。夫を亡くしたのぶが幼なじみの嵩と結ばれる感動的な場面。現代ドラマが描く自立した女性、新しい未亡人像を象徴。
『最後から二番目の恋』シリーズに登場する、魅力的な未亡人たち
『あんぱん』と同様に、未亡人たちが印象的に描かれているのが、今年の春に放送された『続・続・最後から二番目の恋』(フジテレビ系)です。本作は、59歳の独身女性・吉野千明(小泉今日子)と、鎌倉市役所に勤務する63歳の長倉和平(中井貴一)を中心に描かれる物語。特に、長倉和平は多くの未亡人たちから求愛を受けるという特異なキャラクターとして際立っています。
第3シリーズでは、商社マンの夫を亡くした早田律子(石田ひかり)から交際を申し込まれ、千明への思いから和平はこれを断ります。しかし、彼の周囲には、第2シリーズから和平に思いを寄せる鎌倉市長の伊佐山良子(柴田理恵)が控えています。さらに、和平の娘・えりなのボーイフレンドの母親である原田薫子(長谷川京子)も夫を事故で亡くし、和平に惹かれる様子が描かれました。
和平の「未亡人モテ」はこれに留まりません。2012年放送のスペシャルドラマ『最後から二番目の恋2012秋』では、鎌倉市の世界遺産親善大使を依頼した作家の向坂緑子(萬田久子)からも体の関係を求められます。また、第1シリーズでは、弟の嫁の母である大橋秀子(美保純)からも好意を示されています。和平自身も妻を亡くした「寡夫」であるという共通点も、彼が未亡人たちに慕われる一因かもしれません。これらの作品に見られる未亡人たちは、単に悲劇のヒロインとしてではなく、自立し、魅力に溢れ、新たな愛や人生を積極的に求める現代的な女性像として描かれています。
変化する「未亡人像」が映す現代女性の姿
『あんぱん』や『最後から二番目の恋』シリーズに登場する未亡人たちは、夫を亡くしたという共通の経験を持ちながらも、それぞれが異なる形で力強く人生を歩んでいます。これは、単にキャラクター設定の多様性を示すだけでなく、現代社会において女性が自己の価値を再定義し、既存の枠にとらわれずに生きる姿を反映していると言えるでしょう。
悲しみや困難を乗り越え、新たな関係を築いたり、キャリアを追求したり、あるいは自身の内面と向き合ったりする彼女たちの姿は、視聴者に「人生は何度でもやり直せる」「女性はいくつになっても輝ける」というメッセージを投げかけています。これらのドラマは、現代の日本社会における女性の価値観や生き方の変化、そして多様性を肯定する姿勢を鮮やかに映し出しています。