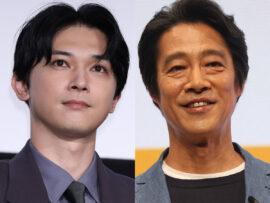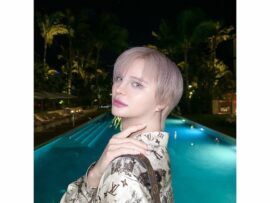多くの人が体感している「離婚が増えている」という現実。しかし、統計データに基づき、実際にどの都道府県でどの程度離婚が発生しているのかを正確に把握している人は少ないでしょう。特に社会問題は、感情論に流れがちであり、「それはあなたの感想ですよね」という意見交換の温床になりやすい分野です。理工系分野のように専門性がなければ参入しにくいわけではなく、漠然としたイメージや自身の経験、思い込みで発言しても、それなりに聞こえてしまうという無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)が潜む恐ろしさがあります。
それゆえに、耳心地のいいキャッチーな意見に惑わされることなく、しっかりと実態を踏まえた発言を心がける必要があります。知らず知らずのうちにとんでもない「モラハラ人間」になってしまうリスクも否定できません。そこで今回は、体感として多くの読者が「増えた」と感じているであろう離婚について、実態に基づいた議論を可能にするため、2013年から2023年までの10年程度の間に提出された婚姻届と離婚届の累計件数をもとに、47都道府県における「身近に発生する結婚に対して、どれくらい離婚が発生しているか」(筆者はこれを離婚の見える化、「離婚化指数」と呼称)を分析し、ご紹介します。
データで紐解く社会問題:感情論ではなく統計を
社会問題について語る際に、個人の経験や感覚のみに依存することは、しばしば本質を見誤る原因となります。無意識の偏見は、自身にとって都合の良い、あるいは強く印象に残った出来事を中心に現実を捉えてしまう傾向を強めます。科学的、統計的なアプローチが不可欠なのはこのためです。「離婚化指数」は、このような個人的な感覚を超え、客観的なデータ(過去10年間の婚姻届と離婚届の累計件数)に基づいて、特定の地域社会における結婚と離婚の発生比率を示す指標です。これは単なる離婚率とは異なり、一定期間内に発生した結婚という「始まり」に対する離婚という「終わり」の割合を示すことで、より日常的な感覚に近い「どれくらい身近で離婚が起きているか」を数値化しようとする試みです。
 日本の「離婚化指数」都道府県別ランキング:2013年から2023年の統計データに基づく
日本の「離婚化指数」都道府県別ランキング:2013年から2023年の統計データに基づく
「離婚化指数」が若者の結婚観に与える影響
この「離婚化指数」という指標は、特にこれから結婚を目指す、あるいは結婚について考えている子どもや若者たちにとって、無視できない意味を持ちます。「身近に発生する大人たちの結婚に対して、どれくらい離婚届が提出されているか」という状況は、その後のライフデザインに少なからず影響を与える可能性があるからです。「結婚の話もよく聞くけれど、それにしても離婚の話を頻繁に耳にする」といった状況が指数として可視化されることで、結婚に対するイメージは大きく変わり得ます。このような環境下では、たとえ結婚への希望があっても、「本当に慎重に進めなければ」「将来が不安に感じられる」と考える若い世代が増える可能性も否定できません。「令和時代の2人」を目指す彼らの瞳に、地元の結婚と離婚の発生状況がどのように映るのか(あるいは映りかねないのか)を、都道府県単位で考察する機会として捉えることが重要です。
最新データと過去との比較:全国平均と高離婚化指数地域
2023年10月に東洋経済オンラインで掲載された「『結婚に対して離婚が多い』都道府県ランキング―カギとなるのは『結婚後の生活』の話し合い」との比較を通じて、最新のデータが示す傾向を確認できます。前回の全国平均は35.4%でしたが、今回のデータでは35.6%と微増(誤差の範囲とも言える)となりました。これは依然として、婚姻届の約35%台に相当する数の離婚届が提出されている(婚姻数の1/3を超える離婚化が進んでいる)という現実を示しています。また、離婚化指数が40%以上を示す自治体の数も、前回調査時の9自治体から今回調査では10自治体へと増加しました。これは、一部の地域で結婚に対する離婚の割合がさらに高まっていることを示唆しており、今後の詳細な分析が待たれる結果です。