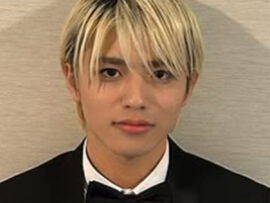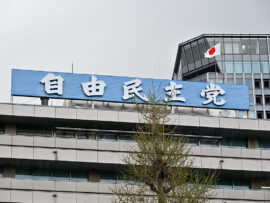NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の第26回は「三人の女」と題され、視聴者の間で話題となりました。この「三人」とは一体誰を指すのか、そして中心人物の一人である吉原の花魁・誰袖と、田沼意次嫡男・意知との関係は史実に基づいているのか、ドラマの内容を深掘りしつつ、その背景を探ります。特に、吉原からの唯一の合法的な脱出手段であった「身請け」という制度にも触れながら、ドラマと史実の境界線を検証します。
「三人の女」は誰か?候補たちの分析
ドラマ第26回で言及された「三人の女」のうち、二人は比較的容易に特定できます。一人は主人公である蔦重こと蔦屋重三郎(横浜流星)の妻である「てい」(橋本愛)。そしてもう一人は、吉原の十文字屋で最高位の花魁である誰袖(福原遥)でしょう。誰袖は今後の物語において重要な役割を果たす人物として描かれています。
 大河ドラマ「べらぼう」の登場人物、吉原の花魁・誰袖(演:福原遥)
大河ドラマ「べらぼう」の登場人物、吉原の花魁・誰袖(演:福原遥)
では、三人目の女性は誰でしょうか。最も有力な候補として考えられるのは、この回から登場し、蔦重の日本橋の店に身を寄せた実母の「つよ」(高岡早紀)です。蔦重の菩提寺である正法寺(東京都台東区)にある供養碑には、江戸の人「諱は津与」と刻まれており、「七歳で母と別れたが後に再会し、一緒に暮らすことができて今の自分がある」という蔦重の言葉が記されています。ドラマで高岡早紀が演じる「つよ」の、江戸の女性らしい描写にはこうした史実が根拠となっています。
しかし、脚本家が想定する三人目が「つよ」ではなく、絵師の歌麿(染谷将太)である可能性も否定できません。ドラマの中で、歌麿は蔦重に「恋心」のような感情を抱いている様子が描かれており、蔦重の妻「てい」に嫉妬する場面もあります。また、「歌麿門人 千代女」という女名で絵を描き、その理由を蔦重に問われた際に「生まれ変わるなら、女がいいからさ」と答えるなど、性別や自己認識に関するテーマが示唆されています。もしドラマの演出意図を重視するならば、三人目の女性は歌麿であるという解釈も成り立ちます。
いずれにせよ、「三人の女」のうちの一人が誰袖であることは確実です。彼女は、花雲助という偽名で吉原を訪れる田沼意次(渡辺謙)の嫡男、田沼意知(宮沢氷魚)に身請けしてもらうことを強く望んでいます。
誰袖と田沼意知、ドラマが描く関係性
ドラマ第26回では、誰袖と意知の間で「身請け」に関する具体的な会話が交わされました。意知が「当分、おいでになれぬ!」と告げると、誰袖は「それでは、身請けの話は?」と矢継ぎ早に尋ねます。意知は、米価の下落による遊興自粛や、若年寄就任による風当たりの強さを理由に、すぐに吉原を訪れることが難しい状況を説明します。
吉原の遊女にとって、客が身代金を支払って遊女の身柄を引き取る「身請け」は、過酷な環境から抜け出すための唯一の合法的な道でした。遊女屋にとっても、身代金は実質的に言い値で決められたため、経営上の大きなメリットとなりました。誰袖が二言目には「身請け」を口にするのは、吉原の現実を反映しています。
ドラマ「べらぼう」では、誰袖は意知から身請けの約束を引き出しています。意知が幕府の直轄領化を目指す蝦夷地(現在の北海道)に関し、管轄する松前藩の密貿易の証拠を集める必要があり、誰袖が情報収集に協力することを条件に、意知が身請けを行うという密約が描かれます。さらにドラマは、二人が逢瀬を重ねるうちに、単なる取引関係を超えて互いに惹かれ合う様子を描写し、恋愛感情が芽生えたことを示唆しています。
続く第27回「願わくば花の下にて春死なん」では、意知は勘定組頭の土山宗次郎(栁俊太郎)の名義で、ついに誰袖の身請けを手配します。武家の女性の装いをした誰袖は、大文字屋を去り、意知との新たな生活に希望を抱きます。しかし、意知は江戸城中で佐野政言(矢本悠馬)に斬りつけられ、屋敷に運ばれるも命を落としてしまいます。誰袖と意知が共に過ごす時間は、叶えられることなく終わるのです。
ドラマの創作か?史実の検証
ドラマで描かれた誰袖と田沼意知の関係は、非常に劇的で物語の中心を担う要素となっています。しかし、様々な史料や文献を調査しても、田沼意知と「誰袖」という名の特定の吉原遊女との間に、身請けの約束や恋愛関係があったことを裏付ける記述は一切確認されていません。
田沼意知が蝦夷地に関心を持ち、その政策を推し進めようとしていたことや、彼が佐野政言に斬殺されたことは史実です。また、吉原に多くの遊女がおり、身請けが重要な制度であったことも歴史的事実です。しかし、これらの史実と、誰袖という特定の遊女が意知と密接な関係を持ち、情報提供の見返りに身請けを約束され、さらに互いに愛し合ったという物語は、大河ドラマ「べらぼう」における創作である可能性が高いと考えられます。
大河ドラマは、史実を基にしながらも、物語としての面白さや人間ドラマを描くためにフィクションを取り入れることが一般的です。「べらぼう」における誰袖と意知の関係は、蔦重の周辺で起こる出来事として、当時の吉原の現実、田沼時代の政治的な駆け引き、そして叶わぬ恋といった要素を織り交ぜるための、強力なドラマチックな装置として機能していると言えるでしょう。
この二人の関係が史実ではないと理解した上でドラマを視聴することで、創作部分が物語にどのように深みを与えているのか、より興味深く楽しむことができるはずです。