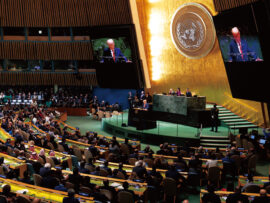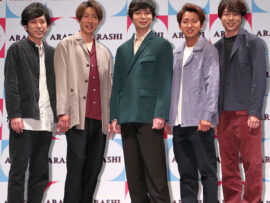開幕から3カ月が経過した大阪・関西万博は、当初、入場者数の低迷や「並ばない万博」という触れ込みとは裏腹の大行列が問題視されたが、足元では入場者数が増加傾向にある。しかし、万博開幕当初からの大きな批判の一つに、「会場内で提供される食事が高すぎる」という声があった。そば一杯3850円、餃子3個2300円といった具体的な例が挙げられ、さらに一部では着席に席料が必要なシステムも登場し、「庶民は来るなというのか」とSNSなどで強い反発を招いた。食い倒れの街・大阪には、安くて美味しい庶民的なグルメが豊富にあるだけに、万博の高額グルメは特に悪目立ちした。では、開幕から3カ月が経ち、この状況はどう変化したのだろうか。本記事では、実際に万博会場を訪問し、話題となった高額グルメの一つである3850円のそばを中心に、その実態と評価を検証する。
 大阪・関西万博会場の飲食エリア。開幕当初、高額なメニュー設定が議論を呼んだ
大阪・関西万博会場の飲食エリア。開幕当初、高額なメニュー設定が議論を呼んだ
3850円「究極の神戸牛すき焼きえきそば」の実態
この高額そばを提供するのは、まねき食品のレストラン「MANEKI FUTURE STUDIO JAPAN」だ。運営会社によれば、意外にもこの商品、そして店全体が好評で賑わっているという。店があるのは、会場の中央部、「静けさの森」西側に位置し、スシローの店舗が隣にある。東西どちらのゲートからも徒歩10分ほどかかる立地だ。飲食店に併設して弁当売場もあり、十数種類の弁当が販売されている。
老舗「まねき食品」と「えきそば」の歴史
まねき食品は1888年創業の老舗駅弁業者。1889年発売の幕の内弁当は「幕の内駅弁の元祖」とされる。そして、同社を象徴する存在が姫路駅の立ち食いそば「えきそば」だ。1949年に発売されたえきそばは、終戦直後の統制品だった小麦粉の代わりにこんにゃくとそば粉を混ぜた麺を開発したのが始まり。その後改良を重ね、現在の和風だしに中華麺という独自のスタイルが確立された。一杯480円から提供されるえきそばは姫路のソウルフードとして親しまれ、市内の繁華街や大阪市内にも出店している。
会場での体験と¥3850そばの詳細
万博店舗では当初、休日には100枚以上の整理券が出るほどだったが、現在は回転率向上と行列短縮のため、店頭に直接並ぶ方式に変更された。この日は平日だったため幸運にもすぐに案内されたが、店内はほぼ満席で賑わっていた。早速「究極の神戸牛すき焼きえきそば」3850円を注文した。着丼したそばには、神戸牛のすき焼きが100グラム乗っており、見た目も豪華だ。温泉卵もトッピングされており、すき焼きのように牛肉をつけて食べることもできる。汁は、和風だしに帆立やハマグリの旨みが加わっているとのこと。姫路駅の素朴なえきそばとは一線を画す、非常に深みのあるスープだと感じた。ラーメンでは一般的な重層的なスープだが、そばではあまり追求されてこなかった領域だろう。えきそばの特徴である黄色い中華麺にもよく合い、そばの新しい可能性を感じさせる商品だ。器には、能登半島地震で被災した石川県輪島市の名産「輪島塗」が使われている。
価格に見合う価値と運営側の手応え
このような内容を考慮すれば、確かに3850円という価格も妥当だと感じられた。同社によれば、「せっかくの万博なので、ここでしか食べられないものを考えた。外国人のお客様にも人気です」とのこと。ユニークな提供物として十分な手応えを得ているようだ。
大阪・関西万博は開幕当初、高額な飲食提供などで批判にさらされたが、入場者数は増加傾向に転じている。そして、一例として検証した3850円の「究極の神戸牛すき焼きえきそば」のように、価格設定の背景には、ここでしか味わえない特別な体験や品質へのこだわりが存在することも明らかになった。高額グルメへの評価は分かれるところだが、万博という非日常空間における体験価値と、提供される内容のユニークさによっては、一部の高額メニューも来場者に受け入れられつつある現状がうかがえる。