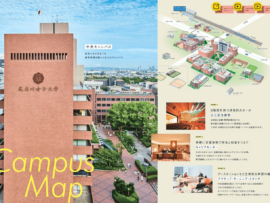鹿児島県トカラ列島近海で続く群発地震は、住民の疲弊を極限まで高めている。「連日のたび重なる地震で、住民の方々は本当に疲弊しています。メディアの方からの取材もお断りしている状況です」と、悪石島診療所のスタッフは語る。6月21日以降、震度1以上の揺れは2000回を超え、うち震度5弱以上の揺れも8回(7月14日現在)に達し、その頻発ぶりに不安と疲労が募るばかりだ。
トカラ列島に迫る群発地震の現実と住民の疲弊
トカラ列島近海で発生している一連の群発地震は、その規模と頻度から、地元住民の生活に深刻な影響を与えている。特に悪石島では、地震の揺れによって商品が棚から崩れ落ちるなどの被害も報告されており、日常生活がままならない状況が続いている。このような地震が頻繁に発生することは、身体的疲労だけでなく、精神的なストレスも住民に大きな負担をかけている。気象庁は南海トラフ地震評価検討会で、このトカラ列島群発地震と将来的に発生が予測される南海トラフ地震との「関連はない」との見解を示しているが、専門家からは異なる意見も出ている。
 トカラ列島群発地震の影響で悪石島の商店の棚から商品が崩れ落ちた様子
トカラ列島群発地震の影響で悪石島の商店の棚から商品が崩れ落ちた様子
プレート活動と流体の役割:科学的見地からの地震発生メカニズム
東京大学地震研究所名誉教授の笠原順三氏は、トカラ列島の地質学的特徴を解説する。「トカラ列島は、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込む境界の西側上部に位置しています。フィリピン海プレートの上に乗った海水を含んだ堆積物が、沈み込みによる地下温度の上昇と圧力により水分を放出し、これがユーラシアプレートの岩石と混ざって通常より低い温度でマグマに変わります。この地下のマグマが海底付近の割れ目を通って上昇し、トカラ列島を南北に押し広げるように動かしていると考えられます」。
この「流体」と呼ばれる海底下の水やマグマは、過去の巨大地震にも深く関与してきた。地震学が専門の東京科学大学理学院教授、中島淳一氏はその影響を説明する。「流体が活断層内やプレートとプレートの境界に入り込むと、潤滑油のような役割を果たし、断層やプレートを動きやすくします。2011年3月の東日本大震災の直前にも、流体によるとされる『スロースリップ』(プレートがゆっくり動く現象)が観測されました。昨年1月に起きた能登半島地震の前に活発だった群発地震も、流体が原因と考えられます」。これらの例は、流体が大地震の引き金となる可能性を示唆している。
国の見解と専門家の警鐘:南海トラフ地震との関連性
気象庁の南海トラフ地震評価検討会は、今後30年以内に80%ほどの確率で発生するとされる最大震度7の南海トラフ地震と、今回のトカラ列島群発地震は「関係ない」と公式に表明している。しかし、防災が専門の関西大学特別任命教授、河田惠昭氏は国の見解に疑問を呈する。「両者とも、フィリピン海プレートが沈み込み、ひずみのエネルギーが溜まることにより起きる地震です。『関係ない』とは断言できないでしょう。むしろフィリピン海プレートの動きが活発化していると解釈すれば、南海トラフ地震の発生リスクは確実に高まっているといえます」。
前出の笠原氏もこれに同意し、「南海トラフ地震の発生確率が高まっている可能性は否定できません。平時より警戒を強めてもかまわないと思います」と警鐘を鳴らす。専門家たちの意見は、政府の見解とは一線を画し、プレート活動の活発化が広範囲な地震リスクの増大につながる可能性を指摘している。
南海トラフ巨大地震の甚大な被害想定と都市部の脆弱性
政府の中央防災会議は今年3月、最大34mの津波が日本列島を襲うとされる南海トラフ地震の被害想定を発表した。この想定によると、死者は最大29万8000人に達するとされる。しかし、河田氏は国の想定にさらなる懸念を示す。「国は地震発生から30分以内に、巨大な津波が太平洋沿岸を襲う場合に人的大被害が発生するとしていますが、津波は都市部にも及びます。発生から2時間以内には大阪市や名古屋市などの市街地にも津波が到達するんです。都市部での津波に対する避難訓練は十分とはいえず、被害は甚大になるでしょう。太平洋の沿岸部でも経験したことのない激しい揺れが1分以上続き、住民が迅速に避難できるとは考えにくい。亡くなる方は災害関連死を含めると国の想定の倍以上、50万〜60万人に達してもおかしくないんです」。
この指摘は、現在の防災対策や住民の避難意識が、現実の巨大地震の脅威に追いついていない可能性を浮き彫りにする。都市部の人口密集度と、津波到達までの時間の短さを考慮すれば、被害が想定をはるかに超えることも十分に考えられる。
巨大地震への備え:危機感を持つことの重要性
トカラ列島の群発地震は、一見すると遠い島の出来事のように思えるかもしれない。しかし、専門家たちの見解は、これが日本の広範な地域に影響を及ぼす可能性のある巨大地震、特に南海トラフ地震の活動の一端である可能性を否定できないと示唆している。政府が「関係ない」と断じることで、緊急時の対応が後手に回る危険性も指摘されている。
私たちは、いつ巨大地震が起きてもおかしくないという危機感を常に持ち、日頃からの備えを怠らないことが極めて重要である。情報の正確な理解と、それに基づいた適切な行動が、未来の甚大な被害を軽減するための鍵となるだろう。
参考資料
- 『FRIDAY』2025年8月1日号
- 東京大学地震研究所
- 東京科学大学理学院
- 関西大学
- 気象庁
- 中央防災会議