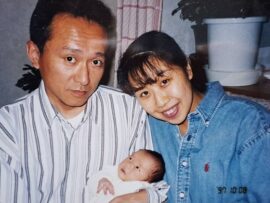近年、日本ではコメ価格の歴史的な高騰と品薄現象が顕著になっています。これは単なる天候不順や一時的な需給バランスの崩れに留まらず、より根深い構造的問題が背景にあると、経済評論家の上念司氏は指摘します。かつて「過剰生産」が課題だった日本のコメ市場は、今や供給不足という新たな局面に直面しています。本稿では、この「コメ不足」現象の多層的な要因と、その根本にある政策的な課題を深掘りします。
 日本のコメ不足と価格高騰を示す食卓の主食、白いご飯のイメージ
日本のコメ不足と価格高騰を示す食卓の主食、白いご飯のイメージ
コメ「過剰生産」から一転、「不足」へ:2023年産の生産量減少と需要の変化
2024年から2025年にかけて、日本はあたかも米騒動を思わせるようなコメ不足に見舞われました。農林水産省が公表した「米に関するマンスリーレポート」によると、2023年産の主食用米の生産量は前年比5.3%減の682万トンにとどまりました。この大幅な減少の主要因としては、度重なる異常気象による収量減に加え、長年にわたり実施されてきた生産調整(いわゆる減反政策)による作付制限の影響が指摘されています。
一方、需要面では顕著な変化が見られます。新型コロナウイルス感染症のパンデミックを契機とした家庭内調理習慣の定着、さらにインバウンド(訪日外国人観光客)需要の急速な回復は、外食産業や宿泊施設におけるコメの消費を押し上げました。加えて、大規模な自然災害が相次いだことで、個人の防災備蓄需要も高まりました。これらの要因が複合的に作用し、2023年度の主食用米の消費量は3年ぶりに増加に転じたのです。供給減少と需要増加という需給のミスマッチは、特に都市部を中心にコメ価格の高騰と在庫逼迫を引き起こし、「コメ不足」現象を顕在化させる結果となりました。
名目廃止後も続く「減反政策」の実態:農業経営の自由を阻む政策誘導
我が国において、1970年代の過剰米問題を背景に導入された減反政策は、名目上は2018年度をもって廃止されたとされています。しかし、その実態は大きく異なります。主食用米から飼料用米、麦、大豆など他の作物への転作を促進するための補助金制度が依然として存続しており、これら政策誘導による作付制限が事実上継続しているのです。
さらに、農林水産省は毎年「適正生産量」の目標値を提示し、JA(農業協同組合)を通じて各農家に対し、作付品目や面積の選択に大きな影響力を行使しています。このような構造の下では、個々の農業経営者の裁量は著しく制限されており、市場の動向や自身の判断に基づいた自由な生産活動が制度的に抑圧されています。結果として、たとえ市場価格が上昇し、需要が高まっている状況であっても、生産量が柔軟に伸びないという「制度的硬直」の構造が形成されてしまっています。
現在の主食用米市場における最大の課題は、市場における価格メカニズムが適切に機能していない点にあります。政策によって価格の硬直性が生じていることに加え、転作へのインセンティブ設計が実際の需要と乖離しているため、供給弾力性が著しく低い構造となっており、これがコメ不足と価格高騰の根源的な原因となっています。
結論:複合的要因と構造的硬直性がもたらす課題
日本のコメ不足と価格高騰は、異常気象による供給減という短期的な要因と、名目上は廃止されたものの実質的に継続している減反政策による構造的な供給抑制という、複合的な問題によって引き起こされています。特に、農業経営の自由を制限し、価格メカニズムの機能不全を招いている政策的な硬直性は、市場の需給バランスを適切に調整する能力を低下させています。この構造的な課題を解決し、安定したコメ供給と価格形成を実現するためには、より柔軟で市場原理に基づいた農業政策への転換が求められています。
参考資料
- 農林水産省, 「米に関するマンスリーレポート」, 各種公表資料.