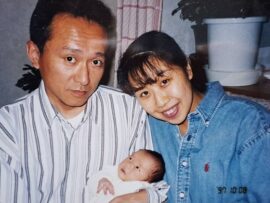第二次世界大戦終結から80年近くが経った今もなお、「もし日本が戦勝国になっていたら、アメリカのような豊かな強国になれたのだろうか」という問いは、多くの人々の間で議論され続けています。しかし、近現代史研究者の分析によると、その道のりは想像以上に困難を極め、むしろ別の形の深刻な問題に直面していた可能性が高いと指摘されています。本稿では、この歴史的仮説を深掘りし、当時の日本が抱えていた内外の状況と、植民地支配がもたらす長期的な代償について考察します。
戦勝国としての「新たな困難」
仮に日本が米英との協調路線をとり、第二次世界大戦で戦勝国の側に回ったとしても、その後の日本が繁栄と安定を享受できたかは断言できません。むしろ、新たな深刻な困難に直面した可能性が指摘されています。例えば、戦後にフランスがアルジェリア戦争やインドシナ戦争といった植民地独立戦争で疲弊したように、日本も朝鮮半島や台湾といった植民地で同様の事態に巻き込まれていたかもしれません。
事実、戦前からこれらの地域では強力な反帝国主義運動が展開されていました。1932年1月には東京で昭和天皇暗殺未遂事件(桜田門事件)が、同年4月には上海で日本の軍関係者や外交官を狙った爆弾テロ(上海天長節爆弾事件)が発生しており、いずれも朝鮮人による犯行でした。もし日本が戦争を回避し、植民地支配を続けていたならば、こうした抵抗運動はさらに激化し、国内外で殺伐とした状況が広がっていたでしょう。
 原爆ドーム
原爆ドーム
また、国内にも不安定な要素が少なくありませんでした。戦前の日本社会は現代と比較にならないほどの格差を抱え、財閥や華族といった特権階級の腐敗や専横はメディアの批判対象となっていました。1932年の血盟団事件(政財界の要人が暗殺された事件)のように、特権階級関係者がテロの標的となる事例すらあったのです。総力戦体制下で一時的にこれらの矛盾は覆い隠されていましたが、もし戦争が避けられていたならば、こうした問題が再び脚光を浴び、国内政治の急進化が加速した可能性も考慮する必要があります。
植民地支配の長きにわたる代償
さらに根本的な問題として、日本が戦前に米英との協調路線を維持し、国内外の混乱を乗り越えたとしても、それが将来にわたって「より良い選択だった」とは言い切れない点があります。確かに現代においても米英は国際秩序の中心的存在ですが、その地位が未来永劫続くとは限りません。近年のトランプ政権下の米国の動向に見られるように、既存の国際秩序は明らかに揺らぎつつあります。500年前の世界に米国という国は存在せず、英国も統一国家としての形を整えていませんでした。今から500年後の世界がどうなっているか、確信を持って語れる者はいません。
そこまで長期的な未来を見通さずとも、より身近な問題も存在します。米英両国には、長期にわたる帝国主義や侵略的領土拡大の過去があります。英国はかつて日本をはるかに上回る規模の植民地帝国を築き、米国は先住民の排除と虐殺を通じて国土を広げました。今世紀に入り、ヨーロッパの旧植民地帝国もようやく、その歴史的責任が問われる時代を迎えています。歴史問題の「優等生」とされるドイツでさえ、正面から扱ってきたのはユダヤ人問題が中心であり、それ以前のアフリカにおける植民地支配については長らく等閑に付してきました。しかし近年では、謝罪や補償を模索する動きが徐々に広がってきています。
このように、歴史が示すのは、植民地支配の代償は必ず支払われるべきものであり、その影響は世代を超えて長く続くということです。日本がもし第二次世界大戦で勝者となっていたとしても、植民地支配の歴史的責任という重荷から逃れることはできず、その解決には多大な時間と労力を要したことでしょう。歴史の「もしも」を考えることは、現在の国際社会が抱える問題や、過去の行動に対する責任の重要性を再認識する機会を与えてくれます。