参議院選挙が20日に迫る中、インターネット上で拡散される情報が有権者の投票行動に大きな影響を与えています。しかし、その中には真偽が疑わしいものや、事実が意図的に歪められた情報が含まれるケースが懸念されています。さらに、こうした情報が機械的に大量に拡散されている実態も明らかになり、世論形成への影響が問題視されています。
「JAPAN NEWS NAVI」アカウント凍結の背景と誤情報の事例
最近、X(旧Twitter)上でニュース記事やSNS上の反応をまとめていると称するウェブサイト『JAPAN NEWS NAVI』と、それに関連すると認定された複数のアカウントが相次いで凍結されました。同サイトは「日本のニュースと日本人の反応をまとめたサイト」と謳っていましたが、一部には誤った情報も含まれており、その投稿が広範囲に拡散されることへの懸念が高まっていました。
具体的な誤情報の例としては、愛知県の大村秀章知事が県のスタートアップ支援に関して「19億円を外国人起業家支援に投入」と掲載された件があります。これに対し大村知事は1日、「嘘を書けば書くだけバズって、書いた人が得をする形というのは、絶対あってはならないこと。ファクトチェックをして、しっかり規制をしていかなければいかん」と反論し、情報の正確性の重要性を訴えました。Xでは「人を欺いたり、損害につながる可能性のあるコンテンツを共有すること」が禁止されており、今回の凍結もこれに抵触した可能性があります。本件に関して、番組がX社と『JAPAN NEWS NAVI』にコメントを求めましたが、現時点での回答は得られていません。
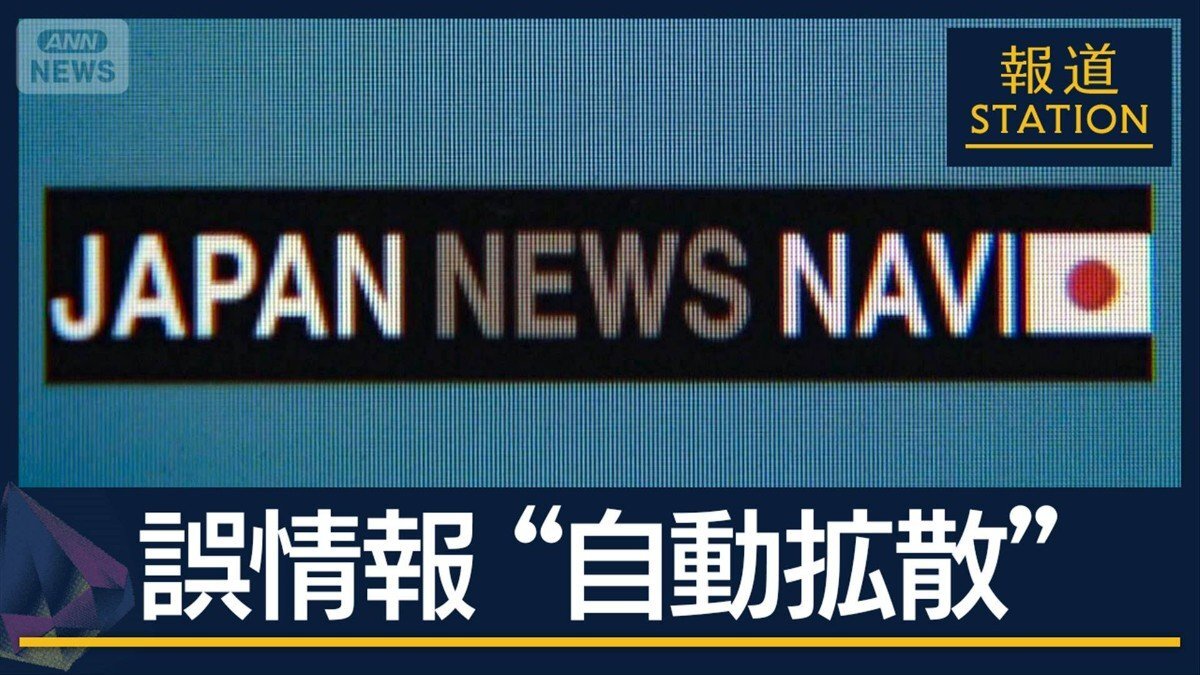 参議院選挙に向けてSNS上で自動拡散される誤情報(フェイクニュース)とボットの活動をイメージした図
参議院選挙に向けてSNS上で自動拡散される誤情報(フェイクニュース)とボットの活動をイメージした図
「自動拡散ボット」の実態と情報操作のリスク
SNS上のデータ分析を手がける『Japan Nexus Intelligence』(JNI)は、前述の『JAPAN NEWS NAVI』の投稿が不審な形で拡散されていることを指摘しています。JNIの分析によると、『JAPAN NEWS NAVI』の投稿を拡散したアカウントのうち、3割以上が機械的に投稿を繰り返すプログラム、いわゆる「ボット」とみられています。
JNIの竜口七彩ヘッドアナリストは、「フォロワーが多いから」「いいね数・リポスト数が多いから」といった理由で投稿の信憑性を高く認識するユーザーが多い現状に対し、「一定程度、情報が水増しされていることを今回の結果を受けて認識の中においてもらえると、情報をとるうえで、ひとつの選択肢になる」と警鐘を鳴らしました。これにより、実際の世論とは異なる意見が多数派であるかのように見せかけられ、有権者の判断を歪めるリスクが浮上しています。
政府の見解と外国勢力介入の難しさ
こうした機械的な情報拡散が進行する中、政府からも懸念の声が上がっています。平将明デジタル大臣は15日、「外国においては、他国から介入をされる事例なども見てとれるので、今回の参議院選挙も、一部、そういう報告もある。検証が必要だと思うが、注意深く見ていく必要がある」と述べ、選挙への外部からの干渉の可能性に言及しました。
しかし、JNIの高森雅和代表は、実際に「外国の勢力」が関与しているかを判断するのは極めて難しいとの見解を示しています。「多くの研究・調査が必要になり、それをしたとしても、この領域で犯人を突き止めるのは非常に難しい」と述べ、明確な特定には至らない場合が多いと説明しました。この発言は、情報源の特定が困難なサイバー空間における課題を浮き彫りにしています。
有権者に求められる情報リテラシー
今回の事態は、民主主義の根幹を揺るがしかねない情報の信頼性という問題に直結します。情報が自動的に拡散され、真偽が不確かなまま人々の判断に影響を与える現状において、私たち有権者一人ひとりに求められるのは、より高度な情報リテラシーです。
JNIの高森代表は、「情報を取ることは大事。そのときに反対の意見とか、一次情報ですよね、元々の情報を見に行く癖をつけないと、偏った意見になってしまうことを理解したうえで、それがあろうがなかろうが『何を信じるか』は、ひとりひとりに委ねられるべき」と強調しています。選挙期間中はもちろんのこと、常日頃から様々な情報を鵜呑みにせず、多角的な視点から吟味し、自らの判断で真実を見極める姿勢がこれまで以上に重要となっています。






