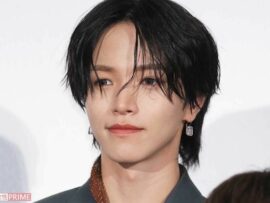「どれだけ頑張っても結果が出ない」「必死に仕事をしても締め切りに間に合わない」――。同僚が次々と成果を上げ、上司からの信頼も厚い中、自分だけが置いていかれているような感覚に陥り、自信を失うことは少なくありません。現在の日本社会では、こうした個人の悩みを超え、組織全体が直面する大きな課題、すなわち「部下が昇進を望まない」という現象が顕著になっています。ビジネススキルに関するTikTokのフォロワー20万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏が提唱する、この現代的な問題の深層と、その解決に向けた具体的な処方箋について解説します。
「管理職になりたくない」という昇進拒否の背景
近年、「マネージャーになりたくない」「マネジメント層にはなりたくない」という理由で転職を選択するケースがニュースでも頻繁に取り上げられています。「自分は一生プレイヤーでいたい」「責任を負いたくない」と考える人が増加傾向にあり、かつては社会全体で「お金を稼ぎたい」「キャリアアップしたい」「承認欲求を満たしたい」といった思いが“正解”とされていましたが、令和の時代ではその価値観が必ずしも当てはまらなくなってきています。
 日本の職場における管理職の課題と部下のキャリア意識
日本の職場における管理職の課題と部下のキャリア意識
部下から見えない上司の「仕事の本質」がギャップを生む
このような状況が生まれる根本的な原因として、西原氏は「上司の仕事が部下に十分に共有されていない」点を指摘します。上司は部下がどのような業務を行っているか、例えば営業活動や事務作業の状況、直面している課題まで把握しています。しかし、部下の側からすると、上司が具体的にどのような仕事に喜びを感じ、どのような苦労を経験しているのか、その「本質」が見えにくいのです。「上司の仕事とはこういうものだ」と積極的に部下に共有している管理職はごくわずかであり、ここに大きなギャップが生まれています。
結果として、部下から見れば「上司はいつも責任が重そうで大変そう」「板挟みになって苦しそう」といった、負の側面ばかりが目につきがちです。これが「昇進したくない」という感情に直結する大きな要因となっています。もちろん、評価制度や報酬面も影響しますが、大半は「上司の仕事の本質が共有されていない」ことに起因すると考えられます。さらに、非公式な交流の場である「飲み会」の機会が減少していることも、上司と部下の間の相互理解を希薄化させ、この問題を深刻化させています。
令和時代に求められる「上司の仕事の見える化」
企業が今後取り組むべきは、部下の仕事を「見える化」することだけでなく、それ以上に上司の仕事も積極的に「見える化」することです。具体的には、上司がどのような思いを持ち、どれほどの熱量で業務に取り組んでいるのかを、月に一度でも部下にシェアする機会を設けることが有効です。例えば、仕事の面白さ、達成感、課題解決へのプロセスなどを率直に語る場を設けるのです。
そうすることで、部下たちは「なるほど、こういうところに面白さややりがいがあるのか」と理解を深め、「自分もいつかは昇進して、この面白さを体験してみたい」と思えるようになるかもしれません。現状では、「よく分からないけど、なんだか辛そう」といった漠然としたイメージだけで昇進を避けてしまう人が多く、特に大企業や上場企業では「部長になって何が良かったのか」といったポジティブな経験談が組織内でほとんど共有されていないのが実情です。だからこそ、「私は部長になって、こういう点が良かった」といった具体的な経験を組織内でしっかりと共有する文化を醸成することが、極めて重要だと考えられます。
結論
現代の日本社会における「管理職への昇進拒否」という課題は、単なる個人の志向性の問題に留まらず、上司の仕事の「本質」が部下に見えにくいという構造的な問題に深く根ざしています。このギャップを埋めるためには、上司自身がその職務におけるやりがいや苦労、そしてそこから得られる達成感を積極的に「見える化」し、部下と共有する機会を創出することが不可欠です。これにより、次世代のリーダー層が管理職の魅力を理解し、自ら昇進を目指す意欲を高めることが期待されます。
本稿は、『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』の著者、西原亮氏の特別寄稿に基づく分析と提言です。