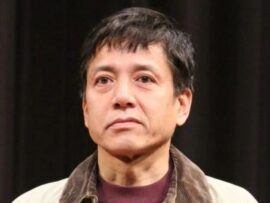東京都中野区鷺宮の閑静な住宅街に、一見コンクリート造りにも見える独特の四角い建物が佇んでいます。これは、1994年に女性洋画家として初の文化功労者となった重鎮、三岸節子のアトリエとして使われていた建物、「三岸家住宅アトリエ」です。都内でも稀少な戦前のモダニズム建築として、その歴史的・文化的な価値が認められ、国登録有形文化財にも指定されています。しかし、長らくあまり使用されずに放置され、一時は相続問題により解体の危機に瀕していました。本稿では、この貴重な文化財がどのようにしてその危機を乗り越え、次世代へと継承される道筋が見えてきたのか、その背景とこれまでの歩みを詳しくご紹介します。
戦前のモダニズム建築の稀少な事例
「三岸家住宅アトリエ」は、昭和初期の日本におけるモダニズム建築の貴重な遺産です。その特異な外観と、日本の洋画史における重要な人物である三岸節子、そしてその夫である三岸好太郎との深い関わりから、建築と美術の両面で注目されています。しかし、この建物は長年にわたりその所有形態や利用状況が不安定であり、特に相続の問題が表面化した際には、取り壊し寸前の状態にまで追い込まれました。
このような困難な状況の中、節子の孫娘である山本愛子さんがこの建物を未来へ残そうと奮闘を始めました。15年以上にわたる彼女の粘り強い努力と献身の結果、2024年に入り、ようやく「三岸家住宅アトリエ」が正式に継承され、保存される具体的な目処が立ちました。この動きは、日本の名建築が全国各地で老朽化し、失われる危機に直面している現状において、文化財の継承と再生の成功事例として大きな希望を与えています。
鬼才・三岸好太郎とバウハウスの系譜
「三岸家住宅アトリエ」の歴史は、画家の三岸好太郎が中心となって始まりました。油彩画における鬼才と称された好太郎は、ドイツのワイマールで1919年に設立され、モダンデザインの基礎を築いたとされる美術学校「バウハウス」で建築を学んで帰国したばかりの山脇巌(やまわき いわお)に設計を依頼しました。好太郎自身も図面作成に深く関わり、1934年に建物は竣工しました。
しかし、完成を目前にした2カ月前に好太郎は名古屋で急逝してしまいます。残された妻の節子は、長兄の経済的援助を受けながら、戦争中も疎開することなくこのアトリエを守り続けました。彼女にとって、この建物は夫が残した最後の作品であり、その遺志を継ぐ大切な場所だったのです。このような背景から、アトリエは単なる作業場以上の意味を持つ、三岸家にとっての特別な存在となりました。
節子の手による増築と建物の変遷
好太郎の死後、三岸節子はこのアトリエに幾度か手を加え、増改築を行いました。当初のアトリエ部分に加え、生活空間としての食堂、浴室、寝室などを増築し、居住性を高めました。その後もアトリエの北側に階段、浴室、トイレといった設備が追加されるなど、建物の機能と形態は節子の生活の変化に合わせて進化していきました。これらの増築は、建物が単なるアトリエではなく、三岸一家の生活の中心地として息づいていたことを物語っています。
孫娘・山本愛子への継承の経緯
三岸節子がフランスに移住したのは1968年のことでした。この時、彼女は息子の黄太郎一家と共に海を渡りましたが、その際に娘の陽子さん(山本愛子さんの母)に対し、「アトリエを残すように」という強い願いを託しました。この節子の遺志を受け、愛子さん一家はそれまで住んでいた練馬区の住居を引き払い、「三岸家住宅アトリエ」へと引っ越してきました。以来、この建物は山本愛子さん一家の住まいとして、そして三岸家の歴史を宿す場所として存在し続けてきました。このアトリエが辿ってきた数奇な運命は、日本の近代美術史と建築史の一端を映し出しています。
結び
東京都中野区にひっそりと佇む「三岸家住宅アトリエ」は、単なる建物以上の価値を持つ、日本の文化遺産です。画家三岸節子と三岸好太郎の芸術的な足跡、そして山脇巌によるモダニズム建築の思想が凝縮されたこの場所は、解体の危機に直面しながらも、孫娘・山本愛子さんの長年にわたる尽力により、ついに継承と保存の道が開かれました。この物語は、古い建物をいかにして次世代に繋ぎ、新たな価値を見出すかという現代的な課題に対する一つの答えを示しています。後編では、この継承に向けた具体的な「再生の道筋」に焦点を当て、その詳細に迫ります。
参照元:
Yahoo!ニュース (元の記事提供元): https://news.yahoo.co.jp/articles/ef5694d0897a0b690a663a4deeace893f61751dc