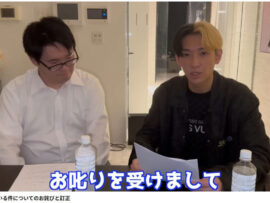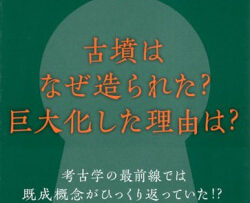テレビCMでおなじみの持ち帰り寿司チェーン、小僧寿しは、1970年1号店出店後、瞬く間に店舗数を増やし、1979年には外食企業トップに輝きました。最盛期には2300店舗を展開し、現在のスターバックスに匹敵する規模でした。しかし、1990年代から閉店が相次ぎ、現在国内は134店舗です。その衰退期は回転寿司の拡大期と重なり、商品面での優位性を示せなかったことが主な要因とみられます。
 新鮮な寿司ネタが並び、手軽に楽しめる持ち帰り寿司のイメージ
新鮮な寿司ネタが並び、手軽に楽しめる持ち帰り寿司のイメージ
持ち帰り寿司市場の成功と拡大
小僧寿しは1964年、「スーパー寿司・鮨桝」として創業。創業者の山木益次氏が米国のチェーンストア理論を導入し、持ち帰り寿司チェーン化を図りました。当初の困難を経て1972年に本部を設立、直営とFCの両軸で店舗数を急増させ、ピーク時には2000店舗を超えました。
商圏を「徒歩や車で10分前後」とし、住宅街やロードサイドへ出店。1970~80年代、飲食チェーンやコンビニが未発達な時代に、手軽な中食として消費者のニーズを捉えました。個人店中心だった寿司業界において、画一性、敷居の低さ、安さが小僧寿し拡大を後押し。「ほっかほっか亭」も同時期に成長しました。
回転寿司の台頭と業績悪化
1993年には全国に2000店舗超を展開していましたが、1990年代後半から店舗数を減らし、業績も悪化。この小僧寿し 衰退原因の背景には、回転寿司の全国的な拡大があります。
価格・立地戦略で競合する中、小僧寿しは商品面で優位性を示せませんでした。
再建の失敗と深刻な財政難
2006年、すかいらーくが小僧寿しを買収し再建を図るも失敗し、2012年に売却。すかいらーくはテイクアウト専業ノウハウや寿司業態経験がなく、シナジー効果は薄かったとされます。
度重なる赤字や、宅配サービス「デリズ」買収によるのれん計上などで2018年12月には債務超過に陥りました。翌年に債務の株式化や新株予約権発行で解消したものの、株価は2004年まで1000円以上を維持後、リーマンショック前後で急落。2016年以降は「ボロ株」と呼ばれる2桁台の超低位株に低迷しています。これは小僧寿し 過去の困難を象徴しています。
まとめ
「小僧寿し」の栄枯盛衰は、日本の外食産業におけるビジネスモデル変遷と市場変化への適応の重要性を示す事例です。手軽な中食市場を切り開き一時代を築いた同社ですが、競合激化(特に回転寿司の台頭)や消費行動変化に対応できず困難に直面。その歴史は、企業が常に市場動向を読み、革新を続ける不可欠性を教えています。